通院や外出に便利な介護タクシーですが「一般のタクシーより料金が高いのでは?」「介護保険は使えるの?」と費用面で不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
結論からいうと、介護タクシーは特定の要件を満たせば介護保険が適用され、費用負担を抑えられます。ただし、誰でも使えるわけではありません。
本記事では、介護タクシーの介護保険適用要件や料金、利用する手順などをわかりやすく解説します。
制度を正しく理解すれば、費用負担を減らし安心して介護タクシーを活用できるため、ぜひ最後までお読みください。
介護タクシーとは

介護タクシーとは、体が不自由な方が利用しやすいよう、車椅子やストレッチャーのまま乗車できる特別な設備を持つ車両での移動サ
ービスです。法的な定義はなく、サービスの通称になります。
介護タクシーには、以下のように介護保険が適用されるタイプとそうでないタイプがあります。
| 介護保険が適用されるタイプ |
|
| 介護保険が適用されないタイプ |
|
このように、同じ移動サービスでも、どちらのタイプかによって料金体系や利用できる条件、受けられる介助が異なります。利用を検討する際は、名称だけでなく「介護保険は使えるか」「運転手は資格を持っているか」などを事前に必ず確認しましょう。
介護タクシーの介護保険適用要件

介護タクシーで介護保険を使うには、複数の要件を満たす必要があります。訪問介護の「通院等乗降介助(文献1)」としての利用となり、利用は日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出に限られます。以下で具体的な要件を詳しく見ていきましょう。
ケアプラン作成
介護保険を適用するには、ケアプラン(居宅サービス計画)に「通院等乗降介助」の利用が位置づけられていることが必須です。ケアプランの作成者が、ご利用者の状況から必要性を判断し、目的地や利用頻度、介助内容などを具体的に計画に盛り込みます。自己判断での利用は保険適用外となるため、まずはケアマネジャーへ相談すると良いでしょう。ケアプランに位置付けられることで、はじめて保険適用での利用が可能になります。
なお、介護保険サービスの利用に関する詳しい解説は、『はじめての高齢者施設ガイド 介護保険制度と老人ホームについて』を参照してください
利用対象者
介護保険で介護タクシーを利用できるのは、要介護1〜5の認定を受けている方に限られており、要支援の方は利用できません。さらに、一人でバスや電車などの公共交通機関を使って移動することが難しいと判断される必要があります。居住場所も、自宅や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの在宅サービス対象の方に限られ、特養のような施設サービスを利用されている方は原則対象外です。
利用目的
介護保険が適用されるのは「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」に限られます。具体例としては以下のとおりです。
- 病院への通院(入院・退院含む)
- 預貯金の引き出し
- 選挙の投票
- 役所での公的な手続き
- 本人確認が必要な補聴器・眼鏡の調整や購入など
一方、趣味や旅行、日常的な買い物、理美容、冠婚葬祭などの目的では利用できません。生活に必要な外出の支援と理解しましょう。
サービス内容
介護保険適用の介護タクシーは、訪問介護の「通院等乗降介助」というサービスです。そのため、単なる目的地への移動だけでは利用できません。
- 車両への乗り降りの介助
- 自宅内での移動介助
- ベッドから車椅子、玄関から車両などの乗車前後の移動サポート
- 通院先での受診手続きの補助
このように、一連の介助と移動がセットになっています。
介護保険適用の際の介護タクシーの料金
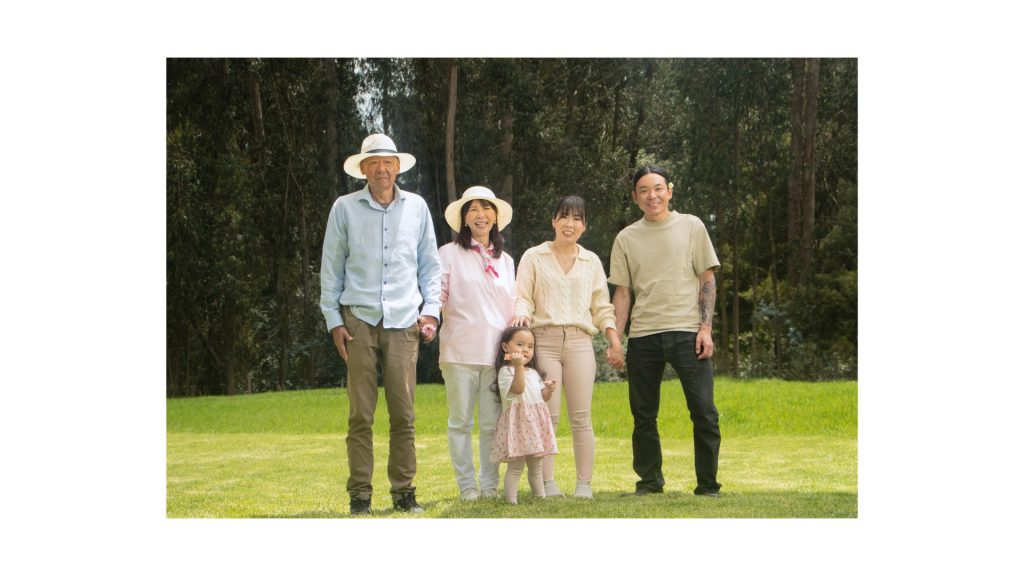
ここでは、介護保険適用時の介護タクシー料金について解説します。保険が適用されるのは介助費用の一部のみで、運賃などは自己負担です。費用の内訳と、利用できる割引制度について詳しく見ていきましょう。
介護タクシーの費用の内訳
介護保険適用時の料金は、以下の表のように3つの項目があります。
| 運賃 |
|
| 介助費用 |
|
| 介護機器レンタル料 |
|
このように介護保険が適用されるのは介助費用のみなので注意が必要です。また、運賃や介護機器レンタル料については、事業者によって異なるため、利用前に確認する必要があります。
介護タクシーで利用できる割引・助成制度
事業者によってリピーター割引のような独自の割引を設けている場合があります。また、自治体によっては高齢者向けに福祉タクシーチケット配布や運賃助成を行っていることがあります。ただし、この助成制度は介護保険適用外のタクシー利用が対象の場合もあるため確認が必要です。
利用可能な制度については、まず担当ケアマネジャーや自治体の福祉窓口、事業者などに直接確認するのも良いでしょう。
介護タクシーを介護保険で利用する手順

介護保険を使って介護タクシーを利用する場合、一般のタクシーのように電話一本ですぐに乗れるわけではありません。計画的な手順を踏む必要があります。
【ステップ1:ケアマネジャーへの相談とケアプラン作成】
まずは担当ケアマネジャーへ相談します。利用する目的や必要な介助内容を伝え、サービスの必要性を判断してもらいます。ケアプランに「通院等乗降介助」が位置付けられることで、サービスを受けられるようになります。
【ステップ2:事業者の選択と契約】
介護保険適用のサービスを提供している介護タクシー事業者を選び、利用契約を結びます。料金やサービス内容をしっかり確認しましょう。
【ステップ3:利用の予約】
利用したい日時が決まったら、事前に事業者へ予約を入れます。利用者の状況や必要な介助内容などを正確に伝えることが、当日のスムーズな利用につながります。
【ステップ4:利用当日】
予約した日時に運転手が迎えに来て、必要な介助を受けながら目的地へ移動します。利用後は、自己負担分の料金を支払います。
このように、介護保険での利用は、ケアマネジャーとの連携と事前の計画が不可欠です。
なお、要介護認定に関するくわしい解説は『要介護認定を受けるには何が必要?申請先や具体的な方法を詳しく解説』をご参照ください。
介護保険適用要件で介護タクシーを利用する際の注意点

介護保険を使って介護タクシーを利用する際には、利用目的や同乗者、運転手の介助範囲には制限があるため、事前にルールを理解しておくことが大切です。以下で具体的に見ていきましょう。
日常生活上または社会生活上必要のない目的での利用はできない
介護保険が適用されるのは「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」のみです。たとえば以下のような目的では利用はできません。
- 趣味やレジャー
- 旅行
- ドライブ
- 日常的な買い物
- 理美容院
これらの目的での利用は保険適用外となります。通院や公的手続きなど、生活に不可欠な外出に限られる点を覚えておきましょう。
介護保険サービス利用の場合、家族の同乗は原則できない
介護保険サービスとして利用する場合、ご家族の同乗は原則できません。理由は、一人で移動が困難かつ家族の援助も得られない方のための制度だからです。例外的に同乗が認められる場合もありますが、必ずケアマネジャーやサービス事業者への事前相談と許可が必要です。無断同乗は保険適用外となる可能性があります。
運転手は病院内の付き添いが原則できない
介護保険利用の場合、運転手の役割は病院の玄関や受付までとなります。病院内の対応は病院スタッフが行うのが基本で、運転手による病院内での付き添いや介助は原則できません。例外的に院内介助が必要と判断されるケースもありますが、こちらもケアマネジャーやサービス事業者への確認が必要です。
まとめ

本記事では、介護タクシーで介護保険が適用される要件を中心に、料金体系や利用手順、注意点について解説しました。介護保険が適用されるのは「通院等乗降介助」として、要介護度や利用目的などの条件を満たし、ケアプランに位置づけられた場合に限られます。
また、料金も運賃部分は自己負担となる点に注意が必要です。利用を検討する際は、まず担当のケアマネジャーに相談し、制度を正しく理解した上で、上手に活用していきましょう。
なお、「いいケアネット」では、介護タクシー利用が必要な方の身体状況や生活スタイルに合った老人ホーム探しも可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
ここでは、介護保険適用の介護タクシーに関するよくある質問を紹介します。
介護タクシーが使えるのは要介護度は何からですか?
介護保険が適用される「通院等乗降介助」サービスを利用できるのは、要介護1~要介護5の認定を受けている方です。そのため、要支援1・2の方は、この介護保険サービスは利用対象外となりますのでご注意ください。他の移動手段や全額自己負担のサービスを検討しましょう。
転院や退院で介護タクシーを利用する場合、介護保険は適用されますか?
退院時の移動は、2022年度より介護保険(通院等乗降介助)の対象となりました。一方、転院については、原則として介護保険の適用外となることが多いです。自治体の判断によることもあるため、事前に確認が必要です。
また、下記のサイトでも訪問介護について詳しく解説されておりますので、ぜひ参考にしてください。
【用語解説】訪問看護の仕組みを知ろう!サービス内容と介護保険・医療保険の違い
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。











