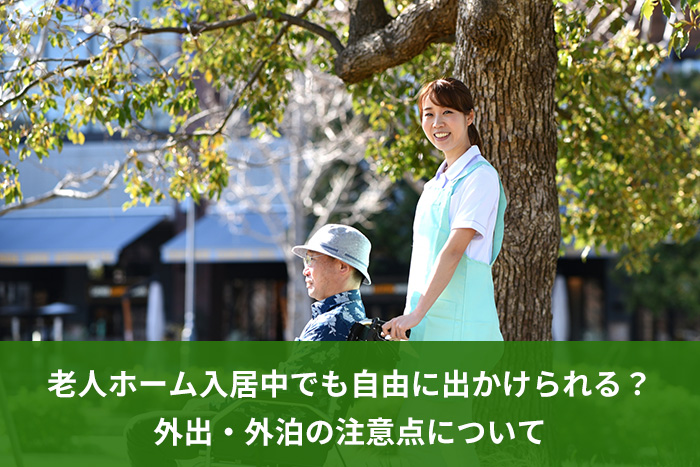「親を老人ホームに入れたいけど、自分の生活もあるから、費用が払えないかもしれない」
「長男が親の面倒を見るべきだと言われているが、弟妹にも少しは負担してほしい」
親の介護は、多くの人に訪れる可能性があります。いざ介護が必要になったとき、費用や責任の所在で悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
老人ホームに入居するには、多額の費用が必要です。親の老後資金や自分たちの負担を心配している人もいるでしょう。所得が少なくても老人ホームの費用を払える方法を知っておけば、ご自身の老後に対する不安解消にもつながります。
この記事では、老人ホームを利用するにあたって必要になる金額と、費用が足りないときの対処法を紹介しています。
老人ホームの支払い義務は入居者本人にある

親が老人ホームに入居するにあたり、費用面で悩む子どもも多くいます。しかし、親の老人ホーム代は親が支払うものです。親の預貯金や年金収入を介護費用にあてるのが基本となります。
親の資産で足りない部分は、子どもたちや親族に負担してもらうのが望ましいとされています。もちろん、子どもや親族にも生活がある以上、自分たちの生活や老後資金を削ってまで、親の介護費用にあてるのは望ましくありません。
兄弟や親族間では誰が多く負担するといった決まりがないため、話し合いによってそれぞれができる範囲でサポートすることが大切です。
老人ホームにかかる費用の目安
老人ホームでの生活には、主に以下の費用が必要となります。
- 老人ホームへ支払う月額費用(家賃・管理費・食費など)
- 医療費、消耗品などの生活費
- 通院介助などの介護保険サービス費
また、入居する老人ホームの種類や要介護度によっても必要となる費用は異なります。各施設における費用の目安は、下表のとおりです。
| 入居一時金 | 月額費用 | |
| 介護付き有料老人ホーム | 0~数千万円 | 14万~35万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 0~数千万円 | 8万~30万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 0~100万円 | 10万~30万円 |
| グループホーム | 0~100万円 | 8万~30万円 |
| 特別養護老人ホーム | 0円 | 5万~20万円 |
| 介護老人保健施設 | 0円 | 8万~20万円 |
| ケアハウス | 0~数百万円 | 7万~30万円 |
生命保険文化センターによる2021年度の調査では、老人ホームに入居している人にかかった1カ月あたりの介護費用の平均は12.2万円です。(文献1)
目安を参考に、入居施設やケアプランを考えると良いでしょう。
また、施設によっては平均余命から算出した居住期間の費用を入居時に請求する一時入居金が必要となる場合があります。一時入居金は月々の家賃の支払いがない代わりに、入居時に数十万円から数千万円支払う必要があるのです。
老人ホームの費用は、立地の良さやサービスの充実度によって高額になる傾向があります。送りたい生活をイメージしながら、介護費用も考慮した老後資金の準備が必要です。
老人ホームの入居時にかかる費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
有料老人ホーム入居の一時金(前払金・入居金・敷金)や月額費用、契約について
費用を抑えた老人ホーム探しを無料で相談するなら「いいケアネット」をご利用ください。
入居者が老人ホームの費用を払えない場合の対処方法

日々の生活に追われ貯金がままならず、老後の資金が心もとない人もいるでしょう。国や自治体制度を利用すると、老人ホームの費用にあてられる場合があります。
ここからは、老人ホームの費用を払えない場合に取れる5つの方法を紹介します。
高額介護サービス費支給制度を利用する
経済的に老人ホームの費用を支払うことが難しいときには、高額介護サービス費支給制度の利用をおすすめします。
高額介護サービス支給制度とは、1カ月に支払った介護サービス費用のうち、自己負担額の上限超過分が支給される制度です。
制度が適用される人には、自治体から申請書が送られてきます。必要事項に記入した上で介護保健課に提出すると、上限額を超えた月の超過分が支給される仕組みです。
高額介護サービス費支給制度では、区分によって自己負担額が異なります。老人ホームの費用が支払えない場合は、下表からどのくらい還付されるかをご確認ください。
| 設定区分 | 対象者 | 月額の負担上限額 |
| 第1段階 | 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
| 15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 | 15,000円(世帯) | |
| 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | 24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
|
| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
| 第3段階 | 市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方 | 24,600円(世帯) |
| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
ただし、介護保険を使用せずに利用したサービスや特定福祉用具購入費などは高額介護サービス費の対象外です。介護に関わるすべての費用に適用されるわけではないことには、注意が必要です。
特定入所者介護サービス費を利用する
老人ホームのなかでも、特別養護老人ホームや介護老人保健施設といった公的施設に入居する際には、特定入居者介護サービス費支給制度が利用できます。
特定入居者介護サービス費とは、所得や資産が一定以下の場合、公的施設の居住費と食費を助成してもらえる制度です。入居者を世帯の年収や資産状況などから4段階に分け、1〜3段階の人を対象に負担限度額が設定されます。
特定入居者介護サービスの区分は下表の通りです。
| 第1段階 | ・生活保護を受給している方等
・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円以下 |
| 第3段階(1) | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円超~120万円以下 |
| 第3段階(2) | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が120万円超 |
| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯 |
※非課税年金を含む
利用するには、各自治体の介護保健課に申請して負担額限度認定を受ける必要があります。負担限度額認定証を受け取り、施設へ提供することで制度が適用されるようになります。
利用者負担の軽減制度を申請する
社会福祉法人が運営する老人ホームでは、利用者負担額が軽減される場合があります。
低所得などで生計を立てるのが困難な人が対象ですが、各自治体に軽減制度の理由を申請し、確認書が発行されると利用できるようになります。
軽減制度の対象となるのは、住民税非課税かつ以下の要件を満たし、生計が困難であると認められた人です。(文献2)
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えることに50万円を加算した額以下である
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えること100万円を加算した額以下である
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族などに扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
利用者負担額の軽減制度を活用すると、介護費用全体の負担額から1/4割引されます。制度を活用できる社会福祉法人は、各自治体のホームページや介護保険窓口から確認可能です。
生活保護を受ける
資産がほとんどなく、老人ホームの費用が支払えない場合には、生活保護の受給も視野に入れておきましょう。年金を受給していても、生活が困窮していると認められる場合には、生活保護を受給できる可能性があります。
介護費用も生活保護の扶助対象です。要支援・要介護認定を受けている場合には、ケアプランを生活保護の担当者に提出して、助けを借りられます。
ただし、生活保護を受給していると入居できない施設もあるため、注意が必要です。一方、生活保護受給者向けに料金プランを作成している施設も存在するため、施設に問い合わせてみることをおすすめします。
生活保護の費用で入居できる老人ホームについては、以下の記事で詳しく解説しています。
老人ホームの費用が払えない場合は生活保護を活用すべき?入居可能な施設の種類を解説
低価格の施設に移る
資産はあるものの、老人ホーム費用の支払いに不安がある場合には、低価格の施設に移ることも検討しましょう。
たとえば、以下のような老人ホームは料金が安い傾向があります。
- 駅から遠く、アクセスが悪い
- 個室ではなく相部屋である
- 施設の建物が古い
また、民間経営の老人ホームよりも、公的施設の方が費用は抑えられます。
施設によっては入居一時金がかからないところもあるため、入居条件は細かく確認しておくことが大切です。
また、現在の施設の入居期間によっては、入居一時金が返金される可能性もあるため、施設側に金額を確認するのがおすすめです。
費用を抑えた老人ホーム探しを無料で相談するなら、大阪を中心とした有料老人ホーム・介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」をご利用ください。
老人ホームの支払いでもめないための対策

「老人ホームに入居してもらいたいのに、費用がない」とならないよう、介護が必要となる前段階から準備しておくことが大切です。
ここからは、老人ホームの支払いでもめないための対策を紹介します。
親の資産を把握する
将来の不安を取り除くためには、親の資産状況を確認しておくことが重要です。
事前に預貯金や借入金の額を把握できていれば、不足の有無や差額分の負担方法について、明確な見通しが立てられるようになります。
お金の話は、仲が良くても聞きづらいもの。普段の会話のなかから少しずつ聞き出したり、将来への不安を打ち明けたりして話してもらうようにします。
親の資産として多いものは以下の通りです。
- 銀行口座(休眠口座の有無も確認)
- 投資有価証券
- 生命保険
- 不動産
負債の有無も確認しておくと安心です。
また、親が認知症になってしまった場合に備え、印鑑や通帳の保管場所をあらかじめ把握しておくことも大切です。
支援する範囲を決めておく
できるだけ親の助けになってやりたいと思っていても、自分の生活がある以上、すべてを負担するのは難しい人も多いでしょう。あらかじめ支援できる範囲を明確にしておくと、希望の介護方法や施設の選び方も変わってきます。
「月に〇〇万円までなら、支援できる」「払える金額は少ないけど、病院の付き添いや家の管理をする」など、兄弟や親戚の間で話し合いの場を持つことも大切です。入居前から負担の割合を決めておくことで、家族間のトラブルを避けられます。
費用や負担の割合に不満がある場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。費用面だけでなく、それぞれ何ができるのかを話しあうようにします。
まとめ|老人ホームの費用は本人が払う!できる範囲の支援で高齢者を支えよう

老人ホームの費用は、原則入居者本人が支払うものです。
老人ホームを選ぶ際には予算を決め、入居者本人の貯金や年金で支払います。足りない部分は子どもや親戚にサポートしてもらいつつ、国や自治体の制度を利用するようにします。
家族は自分の生活を大切にしつつ、共倒れにならないよう、介護の専門家や公的機関に相談するのがおすすめです。
老人ホームの費用を抑えるためには、現在よりも低価格の施設への転居も視野に入れると良いでしょう。
安価で過ごしやすい老人ホームを探すなら、老人ホーム探しの専門家が在籍する「いいケアネット」にご相談ください。
老人ホームの費用についてよくある質問
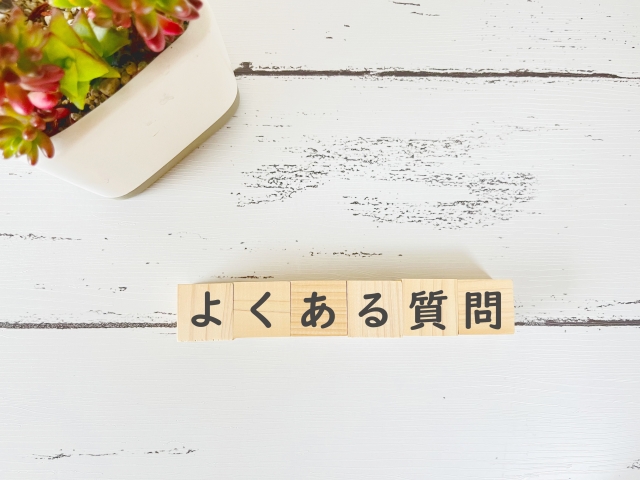
入居中に費用が足りなくなるとどうなりますか?
入居中に老人ホームの費用が支払えなくなった場合は、まず施設の生活相談員や施設長に相談します。分割払いの提案や支払いの猶予を受けられる場合があるためです。
猶予期間も施設によって異なるため、契約書や重要事項説明書を確認するようにします。
費用の滞納が長く続いた場合には、身元保証人に支払い要請が入ったり、強制退去を求められたりします。施設や周囲に多大な迷惑をかけてしまうため、老人ホームの費用が滞納しそうな場合には、介護サービス費支給制度の利用や別施設への転居をご検討ください。
お金がなくても入居できる施設はありますか?
お金がなくても入居できる施設はありません。
民間の施設や公的な施設はかかる費用に差があるものの、入居費や月額費用が必要になります。どこで生活するのにもお金はかかります。
支払えるものがない場合は生活保護受給して、その費用内で入居できる施設を探すようにします。できるだけ費用を抑えて入居できる老人ホームを探すことが重要です。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。