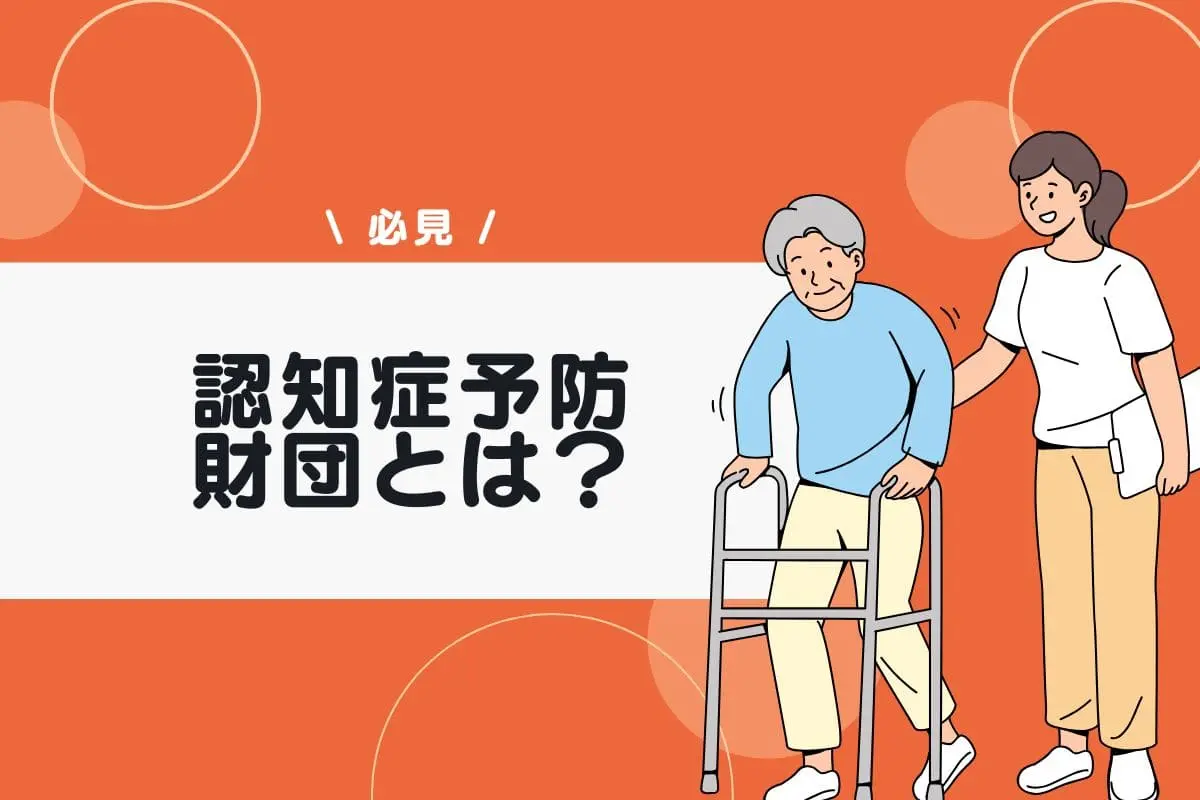「知人から地域包括支援センターの対応が頼りなかったと聞いた…」
「認知症の家族について地域包括支援センターに相談に行ったけど、対応がいまいちだった…」
地域包括支援センターの対応で、がっかりした経験はありませんか。
実は地域包括支援センターの対応には、スタッフの人手不足や経験不足といった背景が影響しています。
本記事では、なぜ地域包括支援センターの対応がひどいと感じてしまうのか、その理由について詳しくご紹介します。
認知症で悩む家族が相談できる、地域包括センター以外の相談窓口や施設についてもご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。
地域包括支援センターとは「高齢者に関する悩み相談窓口」

地域包括支援センターは高齢者やその家族が、地域で安心して生活できるようにサポートする窓口です。
社会福祉士や保健師、ケアマネージャーなどの専門職が対応しており、介護に関する相談や生活支援、介護予防などに関するサービスを提供しています。
近年では認知症地域支援推進員が、医療・介護・福祉のコーディネーターとして活躍しており、認知症に関する相談も気軽におこなえます。
地域包括支援センターの対応が「ひどい」といわれる理由

地域包括支援センターの対応について、「丁寧に対応してくれた」といった意見がある一方で、「対応がひどく不安になった」といった意見も少なくありません。
地域包括支援センターの対応をひどいと感じる背景には、以下のような要因が影響しています。
- スタッフの人手・経験不足
- 業務が多忙すぎる
- あくまでも仲介役である
これから相談を検討している方は、事前に地域包括支援センターの実情や特徴を知っておきましょう。
スタッフの人手・経験不足が対応に影響しているから
地域包括支援センターの設置は、「市町村」または「市町村から依頼を受けたもの」が対象となります。
依頼を受けた法人の中には、経営する介護サービス事業所でスタッフが足りない場合、地域包括支援センターで経験を積んだ職員が異動となります。異動の結果、地域包括支援センターでの経験値が高いスタッフが足りなくなり、経験不足のスタッフが窓口に立つこともめずらしくありません。
また、主任介護支援専門員は5年の経験年数がないと資格を取得できませんが、保健師や社会福祉士は経験年数を問わない国家資格です。経験がまったくない新卒者が、地域包括支援センターに配置されるケースも決して少なくありません。
業務が多忙で相談に十分な時間を割いてもらえないから
高齢化に伴い相談件数は増加傾向にあります。一方で、相談件数に見合うスタッフの人員配置には追いついていません。相談数に対しての人員が足りず、スタッフ一人当たりの業務負担は増えてしまうため、期待する詳細な対応やアドバイスがもらえない状況も考えられるでしょう。
スタッフは実務に加えて受けなければならない研修も増えているため、時間的な余裕のなさから、丁寧な対応が難しくなっている可能性も考えられます。
あくまでも仲介役であり対応に物足りなさを感じるから
地域包括支援センターは、相談や仲介をおこなうのが主な役割です。必要な専門機関への橋渡しはできますが、直接的なサービス提供や医療行為をおこなうことはできません。よって、具体的な解決策まで実施してもらえると期待して相談をすると、物足りなさを感じるかもしれません。
地域包括支援センターで相談する際のポイント

地域包括支援センターの対応が気になって相談を迷っているのであれば、相談前に以下のポイントを意識すると、スムーズに相談を進められるかもしれません。
- 相談内容や質問を整理しておく
- 必要な情報を提示する
本章を参考に、スムーズに相談できるよう準備をしておきましょう。
相談内容や質問を整理しておく
何に困っているのか、どうしたいのかを具体的に整理しておきましょう。
たとえば、以下のように具体的に伝えることが大切です。
- 父の認知症がひどくなり、介護に限界を感じている
- 父が自宅での生活を続けながら、家族の負担も軽減できるサービスがあれば知りたい
また、「どのような支援を受けられるのか」「費用はどれくらいかかるのか」など、地域包括支援センターで対応できることを前もって確認しておきましょう。
地域包括支援センターでは法律に関する専門的な問題や医療行為に関する問題は取り扱っていません。地域包括支援センターでできることにあわせて、できないことも事前に把握しておきましょう。
必要な情報を提示する
相談される際には、医師の診断書や症状の記録(いつから、どのような症状が起こっているかなど)などを提示すると、より具体的にアドバイスを受けやすくなります。
すでに介護認定がおりている方であれば、要介護度や現在利用しているサービスなども伝えておくと、スムーズな対応につながるでしょう。
地域包括支援センター以外に認知症の相談ができる場所

地域包括支援センターへの相談が難しければ、以下に紹介する場所でも認知症についての相談に対応しております。
市町村の福祉課へ相談
市町村の福祉課では、認知症カフェの紹介や地域の福祉サービスに関する情報提供をおこなっています。認知症カフェは、認知症の方やその家族、地域住民、専門家など誰もが気軽に集まる場所です。
認知症カフェでは認知症への理解を深め、認知症の人が安心して暮らせるような地域の活動をおこなっています。場所によっては、オレンジカフェとも呼ばれています。
認知症専門の病院へ相談
物忘れ外来のある病院や、認知症疾患医療センターでは、専門医による診断や認知症の治療を受けられます。認
知症疾患医療センターは認知症に関する医療機関の相談窓口で、都道府県や政令指定都市が指定する病院に設置されています。診断や治療のほかにも、行政や地域の病院などの機関との連携や、認知症についての情報発信をおこなっています。
電話相談
公益社団法人「認知症の人と家族の会」は、認知症の本人や家族、支援者や専門職が集まった団体です。フリーダイヤルの電話相談窓口を設置しており、認知症に関する知識や介護の仕方、介護の悩みなどの電話相談が可能です。
相談機関に話をしに行くのに不安があり、まずは気軽に話を聞いて欲しい場合に利用してみると良いでしょう。
認知症で悩んだら施設への入居も検討しよう

家族の介護負担を軽減するためには、以下のサービスや施設を活用するのも良いでしょう。
- ショートステイ
- グループホーム
- 特別養護老人ホーム
ご家族の認知症に悩んでいる方は、本章を参考に施設の利用も検討してみてください。
ショートステイの利用
ショートステイは数日間施設に入所できるサービスです。介護者の休息や体調不良、急な用事ができた際などに利用でき、家族の介護負担軽減につながります。
ショートステイでは入浴や食事などの日常生活の支援や、機能訓練などの提供がおこなわれます。
認知症の家族との生活を続けたいけど、介護を休憩する時間が欲しい方におすすめのサービスです。
グループホームへの入所
グループホームは認知症の方が少人数で共同生活を送る施設です。入居者のペースに合わせて、できることは自分でおこない、できないことをスタッフでサポートする環境が整っています。
認知症の方の残された能力を最大限に発揮できるような支援を提供し、家庭的な環境でその人らしい生活を手助けする施設です。
グループホームに関する詳しい情報は、以下の記事でもご紹介しておりますので、ぜひご確認ください。
関連記事:グループホームとは?入居条件や老人ホームとの違いを簡単に解説
特別養護老人ホームに早めに申請
自宅での生活が難しくなった場合は特別養護老人ホーム(以下、特養)への入所も検討しましょう。特養とは常に介護を必要とする高齢者が入所する施設です。
特養は利用料が安いため、多くの方が利用を希望されます。希望者が多いため、すぐに入居できるとは限らず、順番待ちとなる期間が数カ月から数年と長期になりやすい傾向です。
将来的に特養への入所を検討されているのであれば、症状が悪化する前に特養へ相談し、入所の申し込みについて進めておくことをおすすめします。
特養に関する情報については、以下の記事にもまとめておりますので、ぜひご確認ください。
関連記事:特養に早く入れる方法【9選】施設選びのポイントから入居待ちの対処法まで解説
まとめ|認知症対応の施設検討も視野にいれよう

地域包括支援センターの対応がひどい理由には、スタッフ不足や多忙な業務が影響しています。
認知症の相談は、地域包括支援センター以外でも市町村の福祉課や専門病院といった窓口で可能なので、必要に応じて利用しましょう。
また、認知症の介護が疲れた際には、家族の負担を減らす目的で施設の検討も大切です。
「いいケアネット」では大阪を中心に全国の介護施設を多数掲載しています。認知症でも入れる近隣の施設をお探しであれば、無料でお手伝いしておりますのでぜひともご活用ください。
地域包括支援センターについてよくあるQ&A
地域包括支援センターについて、よく聞かれる質問をまとめました。
地域包括支援センターではどのような相談ができますか?
地域包括支援センターでは、主に以下のような相談ができます。
- 要介護認定の受け方
- 健康に関する不安
- お金や財産のこと
- 介護が必要な家族のこと
- 近所に住む高齢者のこと
高齢者の生活全般に関わる地域の相談窓口として、さまざまな相談に対応しています。
地域包括支援センターは誰でも利用できますか?
地域包括支援センターの対象者は以下のような方です。
- 対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者
- 40歳〜64歳の方で、特定疾病によって心身の機能が衰えている方
- 高齢者の家族や親族、支援している近所の方
- 高齢者の支援に関わる介護スタッフ
対象地域に住む高齢者とその周りの方々を、幅広くサポートしています。
地域包括支援センターでの相談は予約や利用料金がかかりますか?
地域包括支援センターでの相談は無料です。ただし、相談されたサービスを利用する場合、費用がかかることもあります。また、センターによっては相談が必要な場合もあるため、事前のお問い合わせがおすすめです。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。