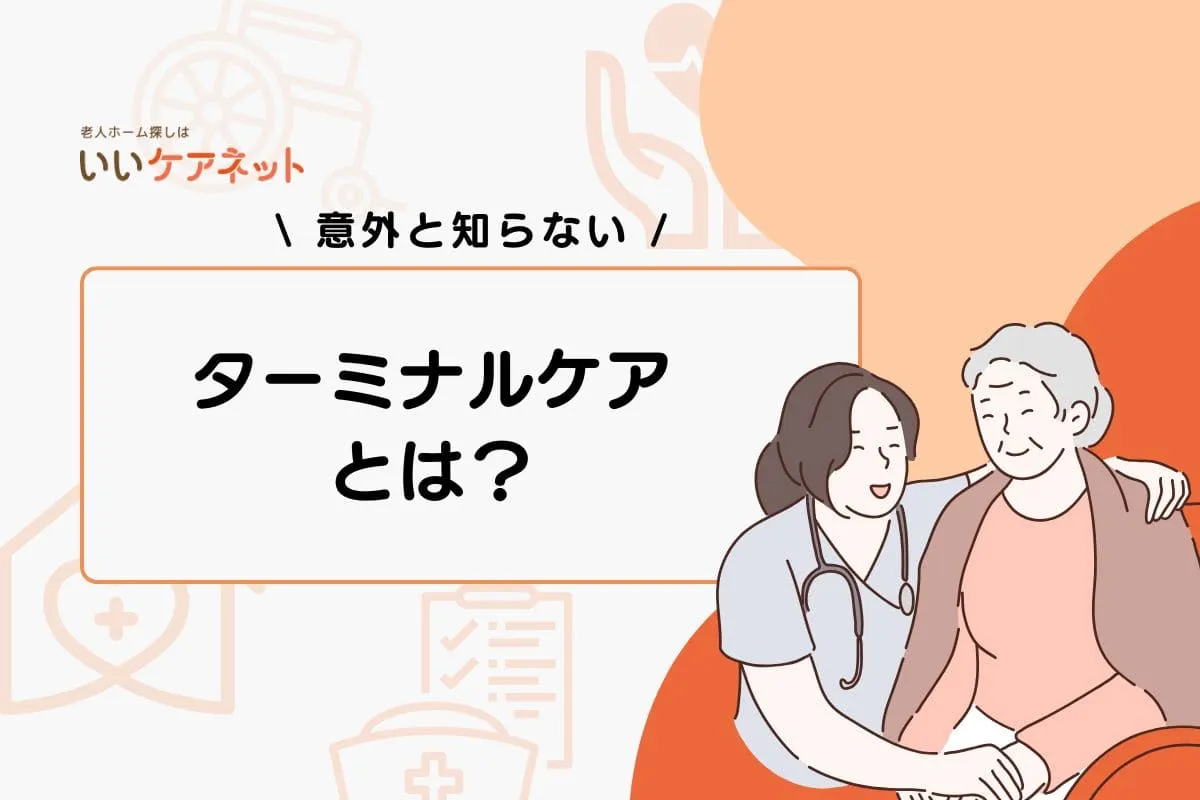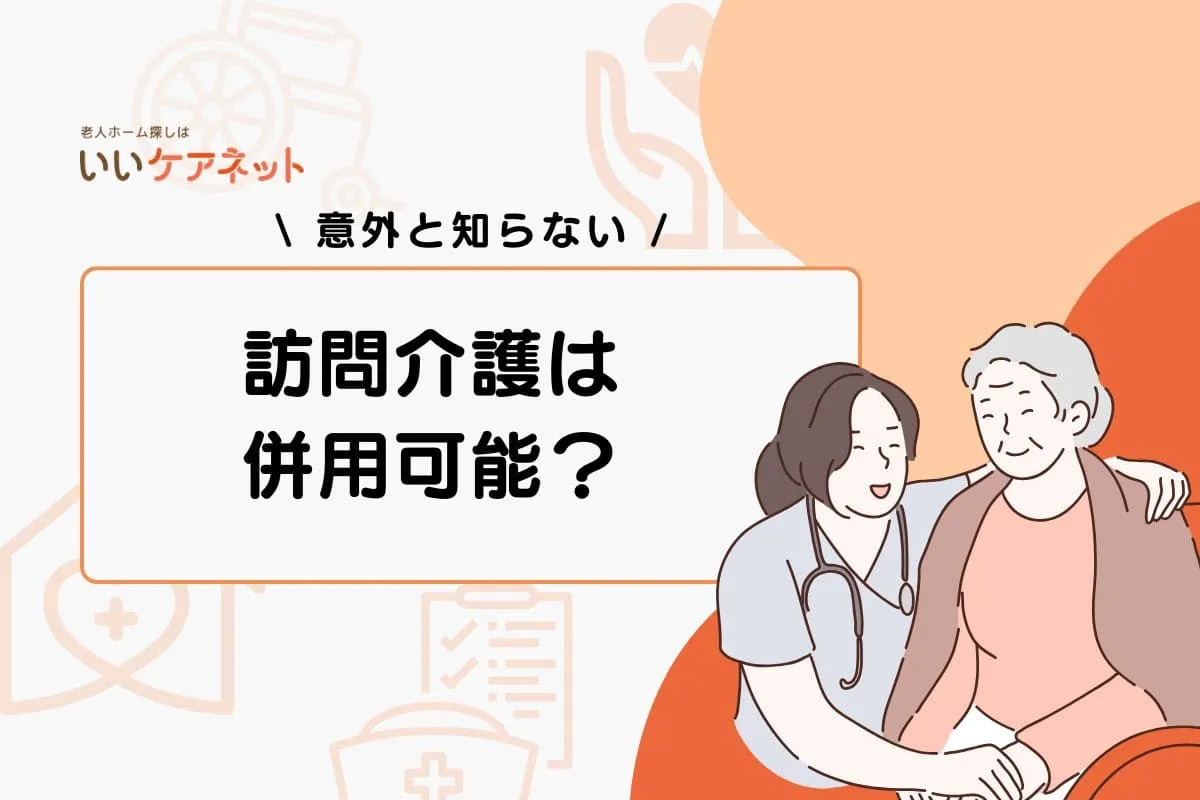「親が要支援1と認定されたけれど、離れて暮らしているから心配…」
「施設入所を検討しているのだけど、要支援1で入れるところはある?」
このような不安を抱えていませんか?
要支援1は、日常生活の動作はほぼ自立しているものの、家事や掃除などで少し支援が必要な状態です。
元気に見えても、遠くに住んでいると「ちゃんと生活できているかな」「何かあったとき大丈夫かな」と心配になるのは当然のことです。
実は要支援1の方でも入居できる施設はさまざまあり、状態や生活スタイル、予算に合わせて選択できます。
この記事では、要支援1の方が入居可能な6つの施設タイプの特徴や費用相場をわかりやすくご紹介します。
将来的に介護が必要になったときに、安心して暮らし続けられる施設選びのポイントをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
要支援1の方も施設入居は可能

要支援1の方も、条件に合えば介護施設への入居が可能です。
要支援1は、日常生活の多くを自分でこなせるものの、部分的に見守りや軽い支援が必要な状態です。
身体機能の低下や軽度の認知症などが原因となり、家での生活に不安を感じる方も少なくありません。
施設では、食事の提供や安全な住環境の確保だけでなく、生活リズムを整えるためのレクリエーションや見守りの支援も受けられます。
健康的な生活を維持しやすくなるほか、孤立を防ぎ、精神的な安定にもつながります。
まだ、元気なうちに入居を決めることで、無理なく新しい環境に慣れやすく、将来的な不安を減らす効果も期待できるでしょう。
どの施設が自分や家族に合っているのか迷ったときは、大阪を中心とした高齢者向けの介護施設情報を多数掲載する「いいケアネット」をご活用ください。
要支援1の方が入所可能な6つの施設

要支援1の方でも入居できる施設はいくつかあります。
それぞれの施設には特徴や費用、提供されるサービスが異なるため、本人の状態や希望や経済状況に合わせて選びましょう。
ここでは入居可能な6つの施設を紹介します。
- 住宅型有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
- シニア向け分譲マンション
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 養護老人ホーム
- 自立型ケアハウス
各施設の特徴や費用相場を解説します。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、「住まい」の提供を中心としながら、食事や生活支援などのサービスが付帯した施設です。
住宅型有料老人ホームの詳しい内容は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 自立した高齢者から要支援・要介護の方まで幅広く対応 |
| 提供サービス | ・食事提供 ・掃除・洗濯・生活支援 ・見守り・安否確認 ・緊急時対応 |
| 費用(目安) | ・入居一時金: 0円~数百万円 ・月額利用料: 10〜50万円 |
介護スタッフは常駐していますが、介護サービスは外部と契約して利用します。
要支援1の方が自立しつつ必要な支援を受けられる環境です。
月額は10〜50万円ほどで、入居金が必要な場合もあります。
将来の介護度の変化にも対応できる施設が多いため、長期的な視点で比較検討するのが安心です。
関連記事:住宅型有料老人ホームとは?主なサービス内容や必要な料金をわかりやすく解説!
健康型有料老人ホーム
健康型有料老人ホームは、自立した生活ができる方を対象とした施設です。
健康型有料老人ホームの詳しい内容は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | ・要支援状態の軽度の方も受け入れ可能 ・認知症や要介護状態になると退去が必要 |
| 提供サービス | ・生活支援 ・趣味・娯楽 ・健康管理 ・自由な生活 |
| 費用(目安) | ・入居一時金: 0円~数億円 (施設の場所や設備による) ・月額利用料: 10万~40万円 (食費、管理費、光熱費などを含む) |
食事や生活相談などの基本サービスはありますが、介護サービスは原則提供されません。
要支援1など介護度が軽い方が対象で、共用施設も充実し、自由度の高い生活が可能です。
月額費用は10〜40万円程度で、入居一時金が高額な場合もあります。
将来的に介護が必要になった際に備えて、介護保険の利用や追加サービスの費用について事前に確認しておきましょう。
シニア向け分譲マンション
シニア向け分譲マンションは、高齢者に配慮したバリアフリー設計を採用した分譲マンションです。
一般的なマンションと同様に購入して所有権を持つことができるため、資産として相続・売却ができます。
シニア向け分譲マンションの詳しい内容は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | ・ 自立した生活が可能な高齢者 ・ 要支援や軽度の要介護者も入居可能だが、介護サービスは外部業者と契約が必要 |
| 提供サービス | ・ 生活支援 ・ 娯楽設備 ・ 居住環境 |
| 費用(目安) | ・ 初期費用: 数千万円~数億円(物件購入費) ・ 月額費用: 10万~30万円(管理費、修繕積立金、サービス利用料など) |
月額管理費は10〜30万円程度で、購入費用は1,000万円〜数億円と幅広いです。
食堂やジム、プールなど共用施設が充実し、快適な生活環境が整っています。
介護サービスは外部事業者の利用が可能な場合もあり、自立した生活を送りつつ将来に備えたい要支援1の方に適しています。
関連記事:シニア向け分譲マンション・ケア付き高齢者住宅とは?魅力や注意点について
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ高住)は、高齢者の安心・安全な暮らしをサポートする賃貸住宅です。
バリアフリー設計が義務付けられており、安否確認と生活相談サービスが必ず提供されます。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の詳しい内容は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | ・ 自立した生活が可能な高齢者、または要支援・軽度の要介護者 ・ 一人暮らしに不安がある方 ・見守りや生活支援を必要とする方 |
| 提供サービス | ・ 必須サービス: 安否確認、生活相談 ・ オプションサービス: 食事提供・外出付き添い・緊急時対応・家事代行など(施設による) ・ 居住環境 |
| 費用(目安) | ・ 初期費用: 敷金として10〜40万円 ・ 月額費用: 10〜20万円程度(家賃、管理費、サービス費、水道光熱費などを含む) |
日中は介護福祉士や看護師などの有資格者が常駐しているため、万が一の際も迅速に対応してもらえる安心感があります。
一般型は初期費用が10〜40万円、月額費用は10〜20万円ほどで利用しやすい価格帯です。
介護型では24時間の見守り体制が整っており、月額15〜40万円程度かかります。
要支援1の方でも、自立した生活を保ちながら必要に応じてサポートが受けられ、将来的な介護にも柔軟に対応できる点が魅力です。
関連記事:サービス付き高齢者向け住宅の問題点とは?失敗しない選び方も解説
養護老人ホーム
養護老人ホームは、経済的・環境的な理由で自宅での生活が困難な65歳以上の高齢者を対象とした公的な施設です。
入居の条件として、市区町村による入所判定が必要になります。
養護老人ホームの詳しい内容は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | ・ 経済的困窮や環境的理由で自宅での生活が困難な方 ・ 入居の可否は市町村が調査・決定 |
| 提供サービス | ・ 生活支援 ・ 自立支援 ・ 居住環境 |
| 費用(目安) | ・ 初期費用: 不要 ・ 月額費用: 0円~14万円(前年度の収入に基づき39段階で設定) |
施設内では食事や入浴などの基本的な生活支援を受けられるほか、レクリエーションなどの社会活動も行われています。
ただし、施設数は限られており入居待ちになることも少なくありません。
入居を検討する場合は、早めに地域の福祉課や地域包括支援センターに相談することをおすすめします。
関連記事:養護老人ホームとは?特養との違いや入所条件、費用負担について解説
自立型ケアハウス
自立型ケアハウス(軽費老人ホームC型)は、60歳以上の比較的自立した生活ができる高齢者のための施設です。
夫婦での入居も可能で、どちらかが60歳以上であれば利用できます。
自立型ケアハウスの詳しい内容は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | ・ 健康状態に大きな問題がなく、介護を必要としない方 ・ 軽度の要支援状態でも入居可能 |
| 提供サービス | ・ 生活支援 ・ 見守り・相談 ・ レクリエーション ・ 外部介護サービス |
| 費用(目安) | ・ 初期費用: 0~30万円程度 ・ 月額費用:9~15万円程度(家賃、食費、管理費を含む) |
入居一時金は0〜30万円、月額利用料は9〜15万円程度と比較的手頃です。
食事や掃除などの生活支援が受けられ、共用スペースも充実しています。
要支援1の方が自分のペースで暮らしながら必要な支援を受けられる環境が整っています。
所得に応じた減額制度や、外部介護サービスの利用が可能な施設もあり、経済的にも安心です。
自立型ケアハウスをはじめ、入居条件や費用に合った施設を探したい方は、大阪を中心とした高齢者向けの介護施設情報を多数掲載する「いいケアネット」をぜひご活用ください。登録無料で、希望に合った施設をスムーズに比較・検討できます。
関連記事:ケアハウスの入居条件は?生活するメリット・デメリットも解説
要支援1の方が入居する施設を選ぶポイント

要支援1の方が施設入居を検討する際に重視すべきポイントがいくつかあります。
選ぶポイントは以下のとおりです。
- かかる費用
- 提供されるサービス内容
- 退居の条件
費用面はもちろん、提供されるサービス内容や将来の状態変化に対応できるかどうかなど、長期的な視点で選ぶことが大切です。
ここでは施設選びの重要なポイントについて詳しく解説します。
かかる費用
施設の費用は大きく「初期費用」と「月額費用」に分けられます。
民間の施設と比べて公的な施設は費用が抑えられる傾向にありますが、入居待ちが長いケースも多いです。
施設別のかかる費用は、以下のようになります。
| 施設の種類 | 初期費用 | 月額費用 |
| 住宅型有料老人ホーム | 0~数千万円 | 10〜50万円 |
| 健康型有料老人ホーム | 0~数千万円 | 10~40万円 |
| シニア向け分譲マンション | 数千万~1億円 | 10~30万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 10〜40万円(敷金) | 10〜20万円 |
| 養護老人ホーム | 0円 | 0~14万円 |
| 自立型ケアハウス | 0~30万円 | 9~15万円 |
月額費用には食費や管理費が含まれていることが多いですが、介護サービス費は別途必要になるケースがほとんどです。
入居一時金が高額な施設では、入居期間に応じた償却制度があり、早期退去の場合は一部返金される場合もあります。
施設見学の際には、将来介護度が上がった場合の費用増加についても確認しましょう。
関連記事:老人ホーム 入居にかかる初期費用
提供されるサービス内容
要支援1の方が快適に生活するためには、どんなサービスが受けられるかをしっかり確認して施設を選びましょう。
施設ごとにサービス内容が異なるため、事前の比較が必要です。
多くの施設では食事の提供や清掃サービスなどの基本的な生活支援は共通していますが、介護スタッフの常駐状況は大きく異なります。
介護付き有料老人ホームでは24時間体制でスタッフが常駐しているのに対し、住宅型有料老人ホームやサ高住では外部の介護サービスを利用する形が一般的です。
また、健康管理やリハビリテーション、レクリエーションの充実度なども施設によって差があります。
社会的なつながりを大切にしたい方は、入居者同士の交流イベントが活発な施設を選ぶと良いでしょう。
退居の条件
要支援1の方が施設に入居する際、将来の状態変化に備えて「退居条件」を事前に確認しましょう。
施設によっては介護度が上がると退去を求められる場合があるためです。
施設ごとの退去条件は以下のとおりです。
| 施設の種類 | 主な退去条件 |
| 住宅型有料老人ホーム | ・ 要介護度が重度化し、施設での対応が困難になった場合 ・ 認知症の症状が進行し、共同生活が困難になった場合 |
| 健康型有料老人ホーム | ・ 要介護状態になった場合 ・ 認知症や医療依存度が高くなった場合 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | ・ 要介護度が重度化し、24時間の介護が必要になった場合 ・ 医療依存度が高くなった場合 |
| 養護老人ホーム | ・ 自立した生活が可能になった場合 ・ 長期入院(例: 3か月以上) ・ 迷惑行為や施設規定違反 |
| 自立型ケアハウス | ・ 要介護度が著しく高くなった場合(例: 要介護3以上) ・ 常時医療的ケアが必要になった場合 |
入居前には「看取りの対応」や「認知症になった場合の対応」などを契約書で確認し、事前にしっかり確認しておくと安心です。
将来を見据えた施設選びのために、不安や疑問は遠慮せず確認し、安心できる暮らしを目指しましょう。
要支援1の方が入れる施設を探して介護の負担をおさえよう【まとめ】

要支援1の方でも、さまざまな高齢者施設への入居が可能です。
住宅型・健康型有料老人ホーム、シニア向け分譲マンション、サービス付き高齢者向け住宅などなど、多様な選択肢があります。
施設選びでは、月額費用や入居一時金などの費用面、生活支援や介護サービスの内容、将来介護度が上がった場合の対応など確認が必要です。
とくに退居条件は施設によって大きく異なるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
要支援1の状態から先を見据えた選択をすれば、本人も家族も安心できる生活環境を整えられます。
まずは見学から始めて、それぞれの特徴をしっかり比べてみてください。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。施設探しに迷ったら、ぜひチェックしてみてください。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。