親の介護が必要になったとき、まず心配になるのが費用面ではないでしょうか。特に在宅介護や施設利用でサービスを多く使うと、月々の自己負担が膨らむこともあります。
そんな経済的負担をやわらげるために設けられたのが「高額介護サービス費」と呼ばれる助成制度です。
本記事では、高額介護サービス費の具体的な内容や申請方法、利用時の注意点をわかりやすく解説します。
高額介護サービス費とは

高額介護サービス費とは、自己負担額が月額上限額を超えた分について、国や市町村から支給される制度です。
この制度の基本的な理解と概要・目的・申請方法・対象となるサービスなどを解説します。
高齢介護サービス費は介護費用の上限を定めた制度
高額介護サービス費は、利用者の負担が1か月に一定額を超えないように設けられている制度です。
同じ月に支払った介護保険サービスの自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超過分があとから払い戻される仕組みになっています。
たとえば月に支払った介護保険サービスの自己負担が5万円で世帯の上限が4万4,400円の場合は、上限を超え5,600円があとから戻ってきます。
介護保険では原則1~3割の自己負担を利用者が支払います。
ただし、要介護度が高い方ほどサービス回数や費用がかさみやすいです。
そこで、高齢者や要介護者の経済的負担を軽減するために高額介護サービス費制度は作られました。
高齢介護サービス費の対象は保険適用サービスのみ
高額介護サービス費で支給対象となるのは、あくまでも介護保険の給付対象サービスにかかった自己負担分だけが対象です。
たとえばデイサービスや訪問介護、特別養護老人ホームの「介護サービス費用」などはカバーされます。
一方で、施設に入所している場合の食費・居住費や福祉用具購入費や住宅改修費の負担額など、介護保険の対象外サービスは補填されません。
介護保険適用分と対象外の費用をしっかり区別しておくと、支給額を把握しやすくなります。
関連記事:介護保険の「負担限度額認定制度」とは?費用負担を軽くする上限とは
上限額は所得や課税状況で計算される
高額介護サービス費で設定される上限額(負担限度額)は、世帯の所得や課税状況に応じて段階的に異なります。
基本的には、以下のように自己負担額の上限が定められています。
- 一般的な課税世帯:44,400円
- 非課税世帯:24,600円、生活保護受給者は個人上限が15,000円
- 高所得の世帯:93,000円や140,100円など
高額介護サービス費の対象となる介護サービス例
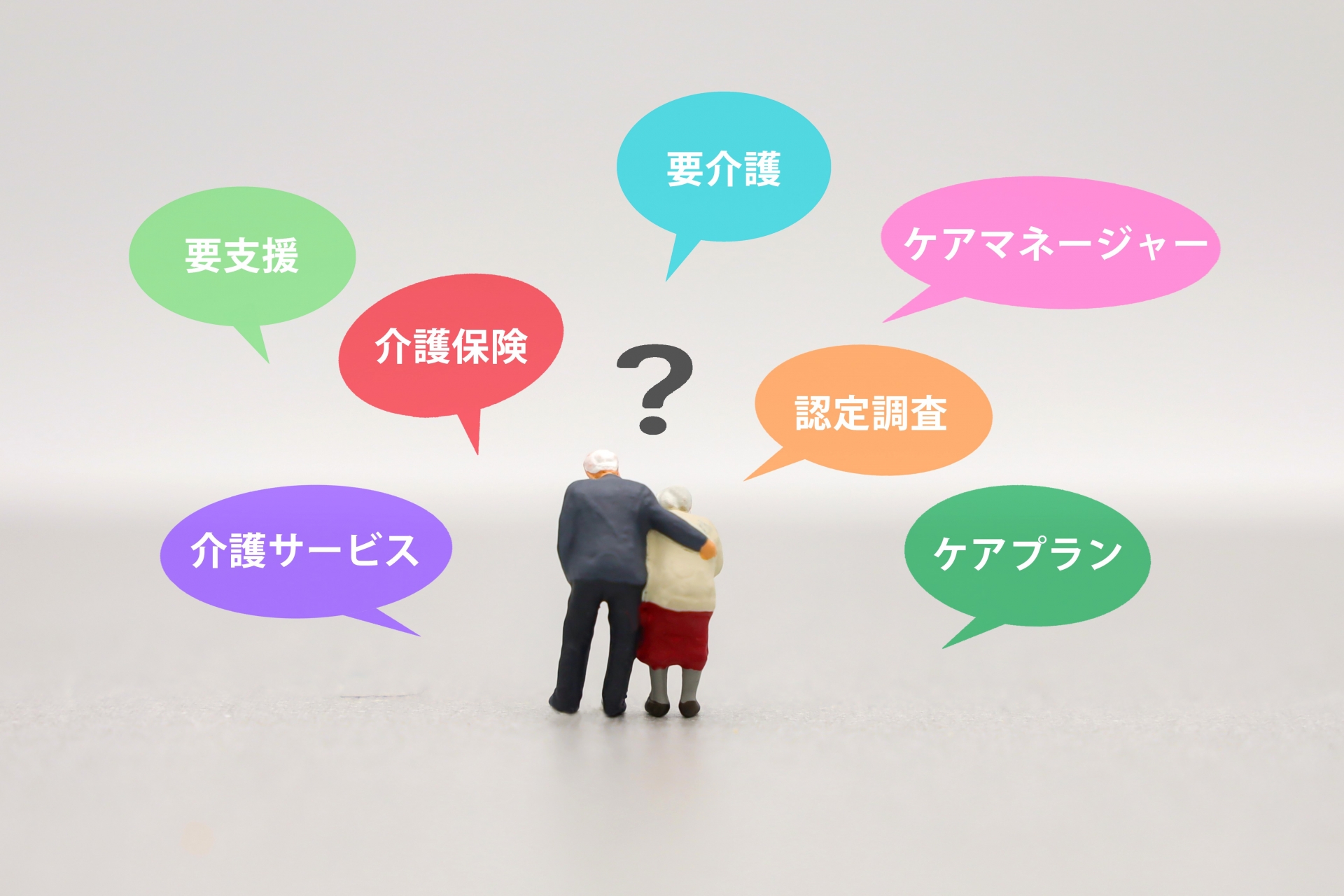
介護サービスは大きく分けて居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3つに分類されます。
いずれも介護保険給付の適用範囲であれば、高額介護サービス費の対象として合算可能です。
以下では、それぞれのサービスにはどのようなものが含まれるかを解説します。
高額介護サービス費対象1.居宅サービス
居宅サービスは在宅で生活しながら、必要な介護や支援を受ける仕組みです。
居宅サービスに該当する代表的なものは以下のとおりです。
- ケアマネージャーによる居宅介護支援
- ホームヘルパーによる訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 訪問看護
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
居宅サービスには、在宅生活を継続したい高齢者や、要支援・要介護の状態でも自宅で過ごしたい高齢者が、不便なく生活できるように支援するサービスが含まれます。
居宅サービスの自己負担分は月々まとめて上限の判定に加算されるため、高額介護サービス費の対象です。
高額介護サービス費対象2.施設サービス
施設サービスは、特別養護老人ホームのような介護施設で、継続的に介護を受けられる形態です。
高額介護サービス費の対象となる施設は、大きく分けて3つあります。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(リハビリを重視する施設)
- 介護療養型医療施設(長期療養や医療管理を必要とする方が対象)
これらの施設に入所している場合でも、医療費のような介護保険の自己負担分は高額介護サービス費の対象になります。
ただし、施設での食費や居住費などは保険適用外となるため、高額介護サービス費の対象外です。
高額介護サービス費対象3.地域密着型サービス
地域密着型サービスは、比較的地域との連携が強い事業所を利用するサービスです。
たとえば、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などがあります。
住み慣れた地域で日常生活を継続しやすい仕組みが整えられており、要支援・要介護の認定を受けた方が対象です。
地域密着型サービスも、介護保険が適用される部分なら高額介護サービス費に含有可能です。
ただし、詳細なサービスの種類や利用方法は自治体や事業所によって異なるため、詳細は各自治体のホームページやお知らせなどをチェックしてください。
関連記事:地域密着型サービス9種類とは?サービス一覧と利用までの流れを解説
高額介護サービス費の対象外なサービス例
高額介護サービス費はあくまでも「介護保険給付にかかる自己負担」が対象です。
そのため、以下のような費用は支給対象外となります。
- 福祉用具の購入費・住宅改修費の自己負担分
- 施設入所時の食費・居住費(滞在費)・日常生活費
- 介護保険が適用されない独自サービスの費用
- 要介護度の支給限度額を超えた分の利用料
これらのサービス料金や費用は保険給付の枠外となるため、実費で支払わなければいけません。
合計で高額になったとしても、高額介護サービス費の計算対象に含められない点に注意しましょう。
参考:横浜市|高額介護サービス費等について
高額介護サービス費の申請方法と手続き

高額介護サービス費は自動的に振り込まれるわけではなく、原則として市町村への申請が必要です。
以下で解説する申請手続きの基本的な流れや提出書類の概要を参考に、必要になったら速やかに申請できるよう、おぼえておきましょう。
高額介護サービス費の手続きに必要な書類
一般的にははじめて利用した月の2〜3か月後に、各自治体から「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」が送られてきます。申請書が届いてからでなければ申請できません。
申請時には、各自治体が求める以下のような書類を提出する必要があります。自治体により提出書類は異なるため、詳細は申請書を確認してください。
- 本人確認書類(運転免許証や保険証など)
- 通帳やキャッシュカード(振込先口座の確認)
- 介護保険被保険者証
- マイナンバーカード
- 利用した介護サービス費に関する領収書など
- 委任状(本人以外が申請する場合のみ)
高額介護サービス費は一度申請すれば、以降の該当月は自動的に振り込まれる自治体がほとんどです。
支給決定通知書が届いたら、振込先や支給額に誤りがないかの確認が大切です。
なお、ただし、住所や口座情報を変更した際は、あらためて手続きが必要とおぼえておきましょう。
参考:ぴったりサービス|【埼玉県さいたま市】高額介護(予防)サービス費の支給申請の手続詳細説明画面
高額介護サービス費申請から払い戻しまでの流れ【本人償還】
高額介護サービス費は、先に全額を支払ったあとで超過分が払い戻される「償還払い」が原則です。
流れは以下のようになっています。
- サービスを利用し、自己負担額をいったん全額支払う。
- 上限額を超えている場合、利用月の2〜3か月後に自治体から申請書が送付される。
- 必要書類を整えて申請すると、さらに1〜2か月後に指定口座へ支給される。
- 一度申請した後は基本的に自動で振り込まれる。
申請期限は利用した月の翌月初日から2年間です。申請期限を過ぎると払い戻しを受けられなくなる恐れがあるため注意しましょう。
本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要となるときもあります。
もし手続きについて不明点があれば、自治体の介護保険担当窓口か、地域包括支援センターなどに問い合わせれば詳細を確認可能です。
直接支払う自己負担額を減らすなら「受領委任払い制度」
毎月の支払いによる負担が生活を圧迫しているような場合は、自治体で受領委任払い制度を利用できるかを確認してみましょう。
受領委任払い制度は、自己負担の上限額を超えたら、自治体が直接事業所などに支払う仕組みです。
利用者は最初から上限額までしか支払わなくて済みます。ただし利用できる自治体や施設は限られており、さらに一定の条件を満たさなければ利用できません。
今後介護サービスを利用する可能性がある場合は、事前に自治体へ受領委任払い制度を利用できるか確認しておくと良いでしょう。
高額介護サービス費について把握した上で介護サービスを利用しよう

高額介護サービス費は、介護保険サービスを利用する上で大きな助けとなる制度です。
上限を超えた場合は後から払い戻されるため、家計の負担が大きくなりすぎないように配慮されています。
ただし、介護施設での食費や部屋代や住宅改修費などは対象外であったり、申請の手間が発生したり、支給されるまでタイムラグがあったりなど、いくつかの不便な点もあります。
自分や家族の負担状況を総合的に確認しながら、必要な制度を賢く活用していきましょう。
高額介護サービス費に関してよくある質問

最後に、高額介護サービス費についてよくある質問と回答を紹介します。
高額介護サービス費の申請をしないとどうなる?
高額介護サービス費は申請しないと支給されません。
申請を行わなければ、上限額を超えても超過分がそのまま自己負担となります。
さらに、申請期限の2年を過ぎると、申請できる権利が消滅してしまうので注意が必要です。
最初に申請してしまえば、翌月以降の対象月は自動で指定口座に振り込まれる場合が多いので、しっかり手続きをしておきましょう。
高額介護サービス費の確定申告で医療費控除を使える?
介護保険サービスの自己負担分は、医療費控除の対象になるケースが多数派です。
しかし、高額介護サービス費で払い戻された金額は、自分が実際に負担した額ではないとみなされます。
そのため、医療費控除を計算する際に「支給された金額は控除対象には含めない」ようにする必要があります。
たとえば施設サービスの費用に介護保険給付が適用され、さらに高額介護サービス費の支給を受けた場合、最終的に自分が負担した金額のみが医療費控除の計算対象です。
二重控除にならないよう、申告時には各金額の内訳を整理しましょう。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。











