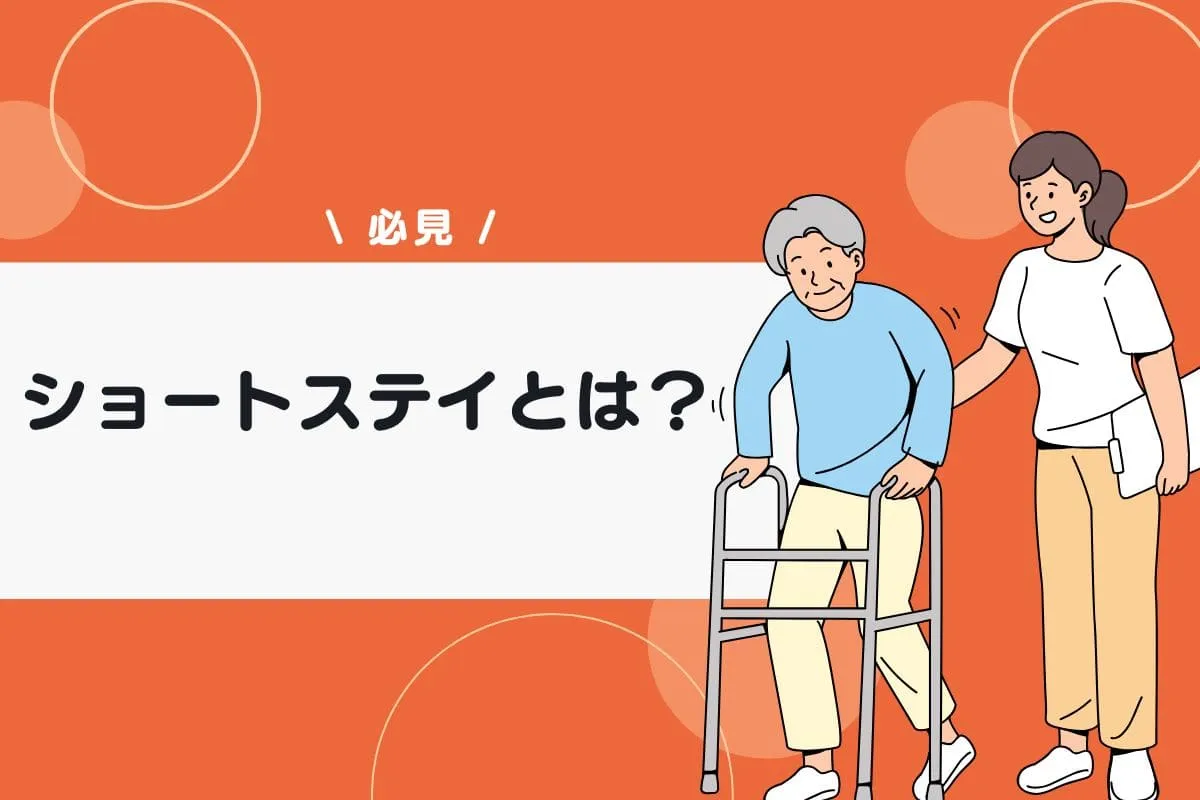身体が不自由で要介護の方や病気療養中につき入浴が大変な方には、手浴を試してみるのがおすすめです。全身の入浴に近い効果が期待できるほか、寝付きが悪いときに行うと快眠効果を得られます。
本記事では、手浴の手順や必要なもの、注意点などについて詳しく紹介します。記事を参考に、手浴をはじめてみてください。
手浴の手順

手浴(しゅよく)とは、名の通り手の入浴です。手は心臓に近い部位のため、手浴で温めれば心臓への血流が促され、全身を素早く温められます。手は、脳が緊張していると冷たくなるため、ストレスを感じている人にこそ必要なケアです。
では、手浴の手順を4ステップで解説します。
- ステップ1.必要なものを準備する
- ステップ2.お湯を適切な温度に温める
- ステップ3.実際に手浴を進めていく
- ステップ4.観察項目をチェックする
1ステップずつ見ていきましょう。
ステップ1.必要なものを準備する
まずは、手浴に必要なものを準備します。
以下に準備するアイテムをまとめました。
| 準備物 | 用途 |
| 洗面器 | 手浴用 |
| バケツ×2 | お湯入れ用 汚水入れ用 |
| ピッチャーまたは、やかん | かけ湯用 |
| シーツまたはバスタオル | 防水用 |
| せっけん | 手洗い用 ※全身浴のものでOK |
| タオル | 拭き取り用 肘の固定用 |
| 水温計 | 温度管理用 |
| クッションまたは枕 | 姿勢の安定用 |
手浴をスムーズに進めるためにも、必要なものを準備しておきましょう。
ステップ2.お湯を適切な温度に温める
手浴をはじめる際に、お湯を適切な温度に温めておきます。
手浴では、38℃〜42℃の温度が適温です。
温めたお湯はバケツの中に入れておきます。蓋付きのバケツを使用すると、お湯の温度が下がりにくくなります。
ステップ3.実際に手浴を進めていく
必要なものとお湯の準備が整ったら、実際に手浴を進めていきます。
以下2つのシチュエーションに分けて説明します。
- ベット上に座って実施する場合
- 寝たまま実施する場合
それぞれの方法を見ていきましょう。
ベット上に座って実施する場合
本人がベット上に座った状態で、手浴する手順は以下のとおりです。
1.上体を起こして、座ってもらう
※膝下にクッションや枕を入れると身体が安定します
2.防水用のシーツ(バスタオル)を敷いて、本人の前に洗面器を置く
3.片手を洗面器の中に入れてもらい、ぬるま湯(38℃)をかける
4.手首までゆっくり浸して、優しくマッサージする
5.手を支えながら石けんをつけたタオルで洗う
6.ピッチャー(やかん)にお湯を入れ、本人にお湯の熱さを確認しながら泡を流していく
7.流し終えたら洗面器のお湯を変えて手をすすぐ
8.手をタオルで包み、洗面器をはずす。
9.乾いたタオルで手の水滴を取り除く
手浴のあとは爪が柔らかくなっているので、爪切りをしてもよいでしょう。また、乾燥肌の人は、化粧水やクリームなどで保湿ケアをしてください。
寝たまま実施する場合
次に、寝たままの状態で手浴をおこなう流れです。手順は以下のとおりです。
1.ベッドの背もたれを高くする
2.肩や腕の下にクッション・枕などを入れて、腕を安定させる
3.本人の体の横に防水用のシーツ(バスタオル)を敷いて洗面器を置く
4.ひじの下に畳んだタオルを入れて手を浮かせる
5.手を洗っていく※洗い方の手順は「ベット上に座って実施する場合」と一緒
必要に応じて、爪切りや保湿ケアをおこないましょう。
なお、臨床現場における手浴の実施時間に関する調査結果では、10分が最も多く、次いで15分程度となっています。手浴に関する明確な時間基準はないものの、臨床の現場での実践例を参考にすると10〜15分が理想的な実施時間と考えられます。
手浴を行う際の3つの注意点

手浴を行う際には、いくつか注意点があります。
- 医師に確認する
- 本人に目的を伝え同意を得る
- 1人で頑張りすぎない
ポイントを押さえて、適切なケアを進めていきましょう。
医師に確認する
手浴をする前には、必ず医師に相談してください。
血流や心拍数の変化を引き起こす効果のある手浴は、体調の悪いときや病気の種類によっては負担となる可能性があるからです。
たとえば、重い心臓の病気がある場合、手浴は身体への負担が大きくなります。感覚麻痺がある方は、お湯の温度を正確に感知できず、火傷してしまうリスクも少なくありません。
医師に相談すれば、手浴の適切な温度や時間など本人の健康状態に合った方法を提案してもらえます。自己判断では行わず、医師の助言を受けて安全に手浴を実施しましょう。
本人に目的を伝え同意を得る
手浴は本人に目的や効果を伝え、同意を得てから実施します。介護の現場では、相手を尊重する姿勢が不可欠であるほか、無理に進めると信頼関係を崩すリスクもあるためです。
以下は手浴の主な目的や効果です。
- 緊張がほぐれ、心身が落ち着き安眠効果も期待できる
- 血流が良くなり、冷えを軽減する
- 衛生状態を維持できる
本人が安心して手浴を受けられる環境を整えるためにも、事前の説明は丁寧に行いましょう。
1人で頑張りすぎない
「衛生管理を徹底しなければ…」の使命感のもと、1人で頑張りすぎてしまうのは注意が必要です。無理して介護を続けると、自身の心身の健康を損ねる可能性があるからです。
介護保険の認定を受けていれば、介護サービスの利用や介護施設の入所も検討できます。心身の疲労を感じたときは、専門のサービスを積極的に活用しましょう。
なかには「親の介護を他の人に任せるのは親不孝なのではないか」と悩む方もいます。しかし、無理をすれば、介護者に負担がかかるだけでなく、本人もストレスを感じてしまう場合があります。
介護サービスの活用は、本人と介護者双方の幸せを目指す前向きな選択肢なのです。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、希望にあった介護施設を探すサポートをいたします。
介護保険制度で受けられるサービスの種類に次いてはこちら
関連記事:介護保険制度とは?~仕組みやサービスの種類・制度の最新情報まで解説~
親の施設入所への罪悪感を払拭させる方法が知りたい方はこちら
関連記事:親を老人ホームに入れるのは親不孝?罪悪感を払拭する方法も解説
手順に沿って手浴を進めてみよう【まとめ】

手浴は、心臓への血流を促し、冷えやむくみなどを解消するケアです。日常的に行えば、身体を良好な状態に保ちやすくなります。
全身浴と比べてケアする側とされる側の負担が少なく、限られた時間の中でも行いやすいでしょう。この機会に、手浴を取り入れてみてください。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、老人ホームや介護にまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
監修者 日本介護福祉教育学会 城田 忠
大阪青山大学介護福祉別科准教授。介護教育と介護留学を専門とし、外国人留学生の介護福祉士国家試験の合格率向上や日本語教育に関する研究を行い、介護福祉業界の発展に貢献。