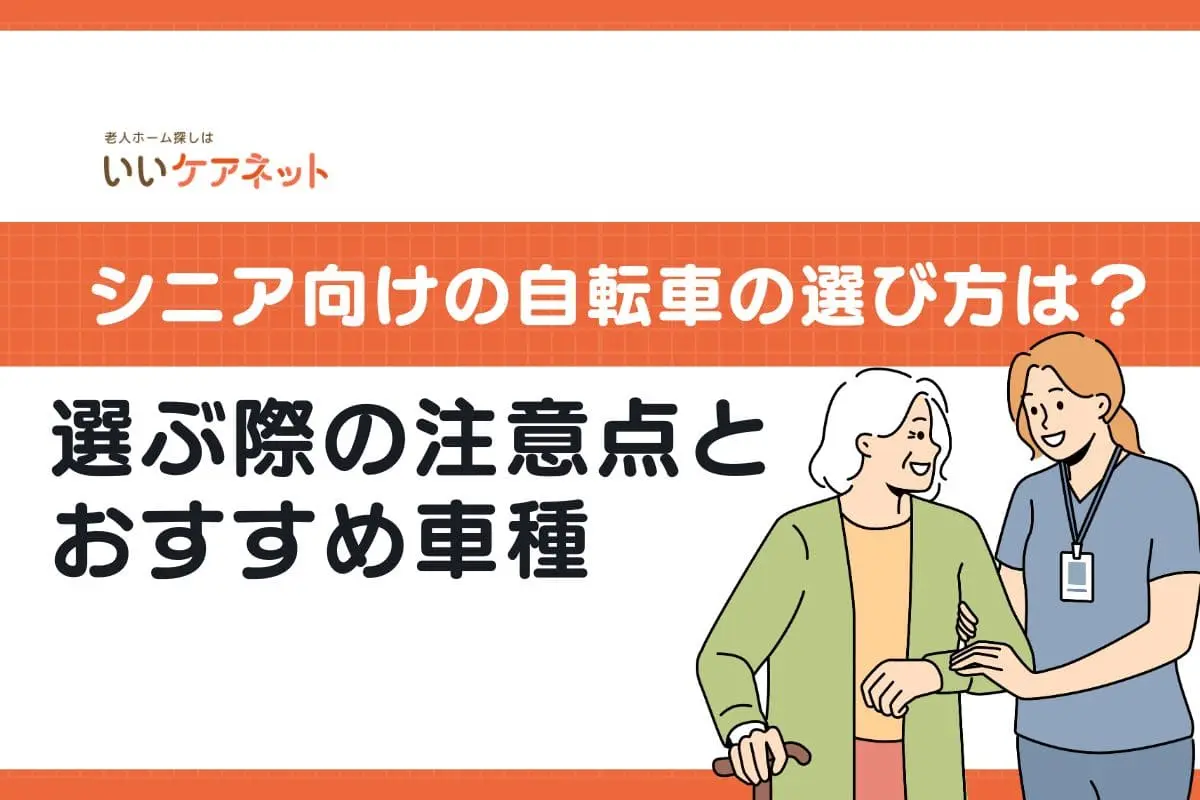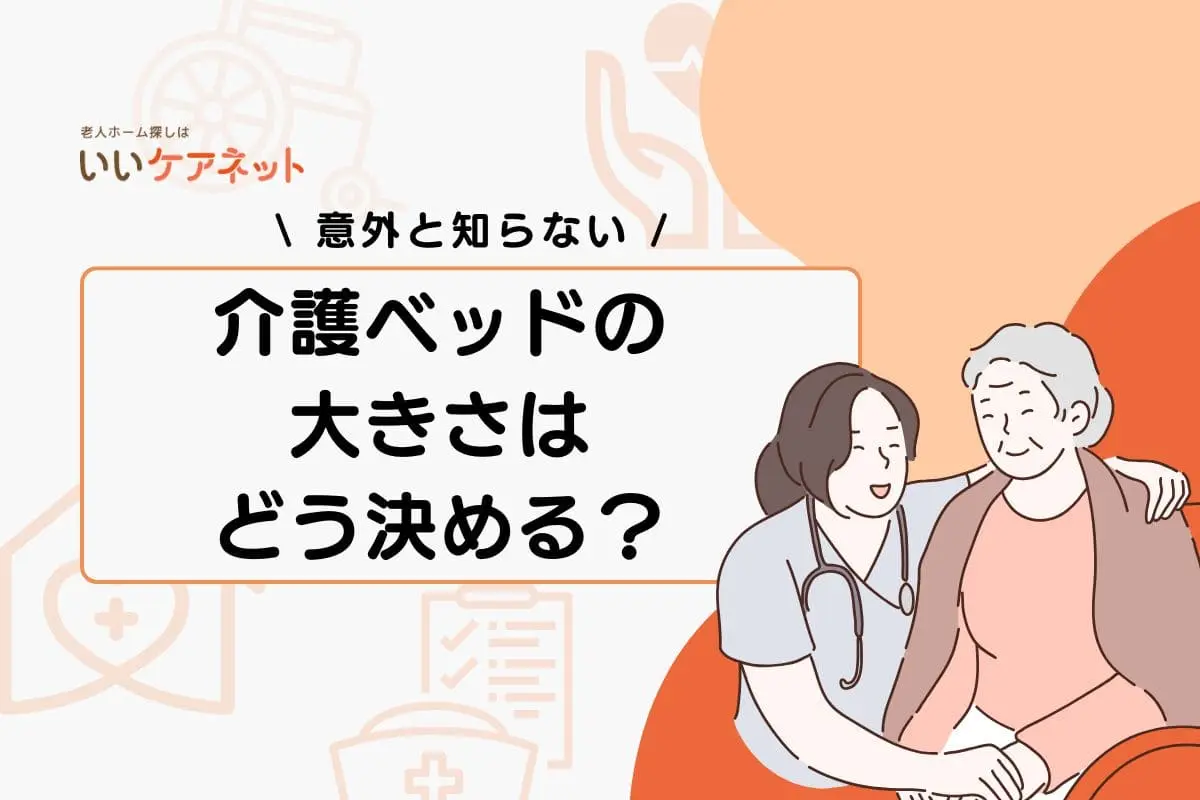「介護保険の認定調査を受けるときのコツはある?」
「要介護度を正しく判定してもらうための注意点はある?」
このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
認定調査は、本人のもとに調査員が訪れ、心身の状態や介護の状況などを聞き取ります。認定調査と主治医の意見書をもとに、要介護認定がおこなわれます。
正しい判定を受けるためには、普段の状況についてのメモを取っておき、家族同席のもとで認定調査を受けましょう。
本記事では、介護保険の認定調査を受ける際のコツを解説します。
注意点や結果に納得できないときの対処法も紹介しているので、要介護度をきちんと判定してもらいたい方は最後までご覧ください。
介護保険の認定調査におけるチェックポイント【全部で74項目】

介護保険の認定調査を受ける際の、基本調査のチェックポイントは以下の74項目あります。
| 第1群:身体機能・起居動作
(20項目) |
1-1 麻痺の有無(5項目) | 1-2 拘縮の有無(4項目) | 1-3 寝返り |
| 1-4 起き上がり | 1-5 座位保持 | 1-6 両足での立位保持 | |
| 1-7 歩行 | 1-8 立ち上がり | 1-9 片足での立位保持 | |
| 1-10 洗身 | 1-11 つめ切り | 1-12 視力 | |
| 1-13 聴力 |
| 第2群:生活機能
(12項目) |
2-1 移乗 | 2-2 移動 | 2-3 えん下 |
| 2-4 食事摂取 | 2-5 排尿 | 2-6 排便 | |
| 2-7 口腔清潔 | 2-8 洗顔 | 2-9 整髪 | |
| 2-10 上衣の着脱 | 2-11 ズボンの着脱 | 2-12 外出頻度 |
| 第3群:認知機能
(9項目) |
3-1 意思の伝達 | 3-2 毎日の日課を理解 | 3-3 生年月日をいう |
| 3-4 短期記憶 | 3-5 自分の名前をいう | 3-6 今の季節を理解 | |
| 3-7 場所の理解 | 3-8 徘徊 | 3-9 外出 |
| 第4群:精神・行動障害
(15項目) |
4-1 被害的 | 4-2 作話 | 4-3 感情が不安定 |
| 4-4 昼夜の逆転 | 4-5 同じ話をする | 4-6 大声を出す | |
| 4-7 介護に抵抗 | 4-8「家に帰る」といい、落ち着きがない | 4-9 一人で外に出たがる | |
| 4-10 物を集めたり、無断でもってくる | 4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする | 4-12 ひどい物忘れ | |
| 4-13 独り言や独り笑い | 4-14 自分勝手な行動 | 4-15 会話にならない |
| 第5群:社会生活への適応
(6項目) |
5-1 薬の内服 | 5-2 金銭の管理 | 5-3 日常の意思決定 |
| 5-4 集団への不適応 | 5-5 買い物 | 5-6 簡単な調理 |
| その他:特別な医療
(12項目) |
1 点滴の管理 | 2 中心静脈栄養 | 3 透析 |
| 4 ストーマ(人工肛門)の処置 | 5 酸素療法 | 6 レスピレーター(人工呼吸器) | |
| 7 気管切開の処置 | 8 疼痛の看護 | 9 経管栄養 | |
| 10 モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度など) | 11 褥瘡の処置 | 12 .カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマなど) |
参考:厚生労働省『認定調査票(概況調査)』
認定調査員は基本項目について、申請者の能力や介助の方法、麻痺と拘縮の有無などの聞き取り調査をおこない、評価します。
関連記事:要介護認定までの流れ、介護保険制度、要支援と要介護の違いについて | 有料老人ホーム・介護施設を探すなら【いいケアネット】公式
関連記事:介護保険申請のベストなタイミングはいつ?流れや必要なものを紹介
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
介護保険の認定調査で正しく判定してもらえる6つのコツ

介護保険の認定調査で正しく判定してもらうには、以下の6つのコツがあります。
- 調査内容をよく確認しておく
- 家族が立ち会う
- 普段からメモをとっておく
- 面会時に表れていない異変も伝える
- 正直に状況を伝える
- 主治医とコミュニケーションをとる
順番に解説します。
調査内容をよく確認しておく
「当日何を聞かれるか」を把握して自分なりに答えをまとめておくと調査のときに、的確に答えやすくなります。
たとえば「座位保持ができますか?」と聞かれたときに「座るくらいはできている」と思っても、調査票の判定基準には以下のようなレベル分けがあります。
- できる
- 自分の手で支えればできる
- 支えてもらえればできる
- できない
とっさに「はい」と答えてしまいがちですが、ゆっくり普段の状態を振り返ると「大体できるけど時々手で支えているな」と思いだせることもあるでしょう。
このように正確に回答するためには、答えをまとめておくと役立ちます。
家族が立ち会う
可能であれば、状況を分かっている家族の立ち合いのもとで調査を受けましょう。
なぜなら、本人の認識と実際に介護している家族との認識がズレている場合があるからです。
また認知症の症状があると、本人では正しく状況を説明できないこともあります。
居宅介護支援事業を利用している場合は、状況を把握しているケアマネジャーに同席してもらうのも良いでしょう。
普段からメモをとっておく
「普段誰が、いつ、どのような介護をおこなっているのか」「困っていること」を整理して、細かくメモをとっておくと役立ちます。
突然質問されると、とっさには答えられなかったり、調査員に伝えたいことがあっても言い忘れたりしがちだからです。
「階段の上り下りには支えがいる」「自分で起きあがるのは難しくていつも家族が支えている」など、整理してみましょう。
また「自宅が狭くて車いすで移動ができない」といった住環境の限界や、既往歴についても説明すると、聞き取り調査だけではわからないことも伝えられます。
困っていることに関しては「要介護者が困っていること」「介護家族が困っていること」の2つに分けて整理しておくとスムーズです。
面会時に表れていない異変も伝える
聞き取り調査では「普段は答えられない」「同じことを繰り返す」など、正確な状態を伝えてください。
特に認知症の方によく起こることですが、調査員の聞き取りの時には気を張って、ご本人がしっかりと回答するということがあります。
たとえば、普段自分の年齢を言えない方が調査員の質問にはしっかり「〇歳」と答える、意思の伝達がスムーズなどです。
しっかりやり取りできるのは良いことですが、正確な介護認定のために、普段の状態を伝えましょう。
正直に状況を伝える
事実に反する回答をしてしまうと、介護状態が軽いと判断されてしまうことになりかねないため、できないことはできないと正直に伝えましょう。
本人が体面を気にしてつい「できる」と言ってしまいがちなときは、普段の状況をメモしておき、調査員に渡すのも方法の1つです。
本人に少し席を外してもらって、調査員に「本当はできないんです」と正直に伝えるのも良いでしょう。
また、普段は掃除に手が回らないのに調査員が来るからときれいに部屋を片付けないようにします。
荒れた部屋で来客を迎えてください、というわけではないのですが、無理に取りつくろう必要はありません。
正しい認定のためには「調査員に現状を知ってもらう」ことが重要です。
主治医とコミュニケーションをとる
要介護認定の判定には「調査結果」のほか「主治医の意見書」にもとづいておこなわれるため、主治医とのコミュニケーションも正しい介護認定を受けるにあたって大切です。
要介護者本人の状況をしっかり把握している主治医から意見書を作成してもらえば、適切な介護度の判定につながります。
介護保険の認定調査でやってはいけないこと

介護保険の認定調査では、高い介護度での認定を受けるために嘘をついてはいけません。
実際よりも悪い状況を申告して必要以上の介護を受けると、自力での行動が減ってしまい、身体機能の低下や認知症の悪化にもつながります。
要介護者本人に適した介護サービスを受けるため、認定調査は正しく回答しましょう。
介護保険の認定調査の結果に納得できない場合の対処法

要介護認定の結果に納得できない場合は「不服申し立て(審査請求)」や「区分変更申請」といった方法があります。
「不服申し立て」が認められれば、行政処分の取り消しと審査のやり直しが可能ですが、完了まで数カ月かかる場合もあります。
もう一方の「区分変更申請」は、ケガや病気の進行により介護度が変わった場合の手続きです。
本人の状態と要介護度があわない場合に受理されるため「不服申し立て」ではなく「区分変更申請」をするケースもあります。
介護保険の認定調査におけるコツを知って必要な介護サービスを受けよう【まとめ】

介護保険の認定調査で正しい判定を受けるコツは、調査内容をあらかじめチェックした、家族立ち合いによる調査です。
現状をありのまま話せば良いのですが、できないことを隠してしまったり、とっさに尋ねられてうまく答えられなかったりする可能性もあります。
普段の状況をメモして渡す、本人不在のときに正直に話すのも有効です。
認定調査の質問シートは事前に把握し、調査員に現状をしっかり伝えましょう。
大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一
大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。