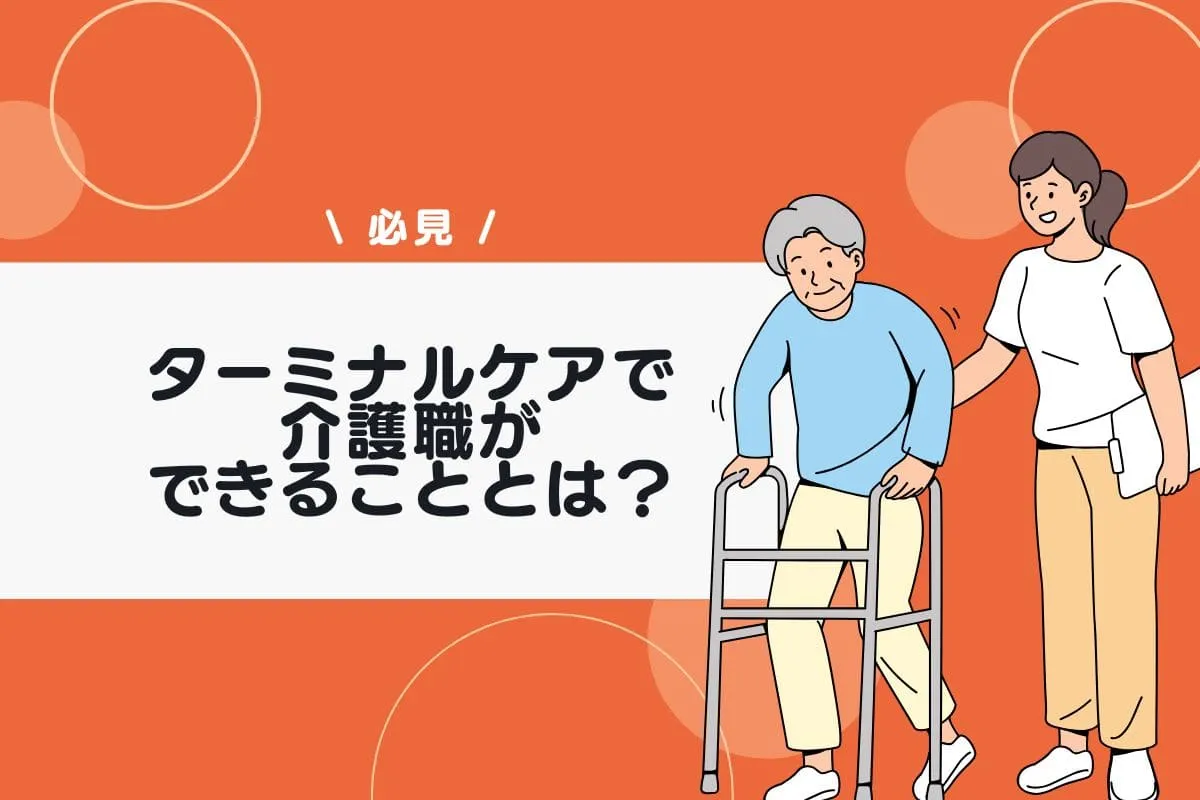老健とは「介護老人保健施設」の略称で、厚生労働省の定義によれば、病状が安定期にある要介護者に対して、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを提供する施設を意味します。病院を退院した後、すぐに自宅での生活に戻るのが難しい方が、在宅復帰を目指して心身の機能回復を図るための「中間施設」と位置づけられています。
この記事では、老健の役割やサービス内容、費用、特別養護老人ホームとの違いなどをわかりやすく解説します。
介護老人保健施設(老健)は在宅復帰を目指すリハビリ施設

介護老人保健施設(老健)が担う最大の役割は、利用者の「在宅復帰」を支援することです。その目的を達成するため、病院での治療を終えた方と自宅での生活をつなぐ橋渡しとしての機能を持っています。
医師や看護師、理学療法士、作業療法士といった専門スタッフが連携し、個々の状態に合わせたリハビリ計画を作成・実施します。福祉サービスとしての介護に加え、医療的管理下で集中的なリハビリを提供することで、利用者が再び自立した日常生活を送れるようにサポートする施設です。
老健に入居できる対象者と利用期間

老健に入所できるのは、原則として65歳以上で要介護認定を受けている方です。病状が安定し、病院での入院治療の必要性はないものの、在宅での生活に向けてリハビリが必要な状態の方が対象となります。
在宅復帰を目的としているため、利用期間には期限が設けられており、終身にわたっての入所はできません。個々の状態に合わせてリハビリ計画が立てられ、定期的に在宅復帰の可能性が検討されます。
入居対象となる具体的な条件
老健の入居対象者は、原則として65歳以上で、要介護1から要介護5までのいずれかの介護度区分に認定されている方です。また、40歳から64歳までの方でも、特定疾病が原因で要介護認定を受けていれば対象となります。入院治療の必要がない安定した病状であることが前提で、在宅復帰への意欲があることが求められます。
特別養護老人ホームが原則要介護3以上であるのに対し、老健は比較的低い介護度から利用できる点が特徴です。ただし、施設によっては医療依存度の高さや認知症の症状によって受け入れが難しい場合もあるため、事前の確認が必要です。
原則3〜6ヶ月という入居期間について
老健は在宅復帰を目指すための施設であるため、入居期間は永続的ではありません。原則として3ヶ月から6ヶ月程度が目安とされており、長期的な入所は認められていません。
入所後は3ヶ月ごとに、身体機能の回復状況や在宅生活の準備状況などを評価し、退所できるかどうかの判定会議が行われます。リハビリによって在宅復帰が可能と判断されれば退所となり、まだ継続が必要と判断された場合は入所が延長されます。
この期間内に、本人や家族はケアマネジャーなどと連携し、退所後の生活に向けた準備を進めていくことになります。
老健で受けられる5つの主要サービス

老健では、利用者が安全に在宅復帰を果たし、自立した生活を再開できるよう、多岐にわたるサービスが提供されます。医師による医学的管理のもと、看護・介護、リハビリテーション、栄養管理、日常生活の支援などが一体的に行われるのが特徴です。
これらのサービスは、入所者一人ひとりの心身の状態や目標に合わせてケアプランとして計画され、多職種の専門スタッフが連携して提供します。単なる身の回りの介護だけでなく、心身機能の維持・回復を目的とした支援が中心となります。
在宅復帰に向けたリハビリテーション
老健のサービスの中核をなすのが、専門スタッフによるリハビリテーションです。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが配置されており、個々の利用者の状態に合わせて「歩く」「立ち上がる」といった基本的な動作訓練から、食事や着替え、トイレなどの日常生活動作(ADL)訓練、さらには嚥下(えんげ)訓練や発声練習まで、専門的なプログラムを提供します。
週に2回以上の個別リハビリが義務付けられており、集中的な機能回復訓練を通じて、在宅生活に必要な心身の能力を取り戻すことを目指します。
医師や看護師による医療的ケア
老健には常勤の医師と、24時間体制で看護師が配置されており、日々の健康管理や医療的ケアが受けられます。具体的には、日々のバイタルチェックや服薬管理、褥瘡(じょくそう)の処置、インスリン注射、喀痰(かくたん)吸引、経管栄養といった医療行為に対応可能です。
病院のように高度な治療は行えませんが、体調の急な変化にも迅速に対応できる体制が整っています。
退院直後で医療的な管理が必要な方や、持病を持つ方でも安心してリハビリに取り組める環境が提供されています。提供可能な医療行為の範囲は施設によって異なるため、事前に確認が必要です。
食事や入浴などの日常生活における介護
介護福祉士や介護職員によって、食事、入浴、排泄、着替えといった日常生活全般にわたる介助が提供されます。老健における介護は、単に身の回りのお世話をするだけでなく、リハビリテーションの一環として行われるのが特徴です。
可能な限り本人の残存能力を引き出し、自分でできることを維持・向上させる「自立支援」の視点が重視されます。
例えば、安全な環境で見守りながら入浴してもらう、一部介助のもとで自分で食事を摂るといった仕組みを通じて、在宅復帰後の生活を想定した支援が行われます。
管理栄養士による栄養管理と食事提供
管理栄養士が常駐し、利用者の栄養状態を適切に管理することも重要なサービスの一つです。一人ひとりの健康状態や病状、嚥下(えんげ)機能に合わせて、栄養バランスの取れた食事が提供されます。
糖尿病食や減塩食といった治療食や、食べ物を細かく刻んだ「刻み食」、ミキサーにかけた「ミキサー食」など、様々な食事形態に対応しています。
適切な栄養管理は、リハビリ効果を高め、体力の回復を促進するために不可欠です。その他、季節感のある行事食などを通じて、食事の楽しみも提供しています。
退所後の生活に関する相談や支援
老健の最終目標である在宅復帰をスムーズに進めるため、支援相談員(ソーシャルワーカー)が中心となって退所支援を行います。本人や家族と面談を重ね、退所後の生活に関する不安や希望をヒアリングし、ケアマネジャーと連携して在宅介護サービスの調整を進めます。
具体的には、訪問介護やデイサービスの利用手続き、福祉用具のレンタルや住宅改修に関するアドバイスなどを行います。退所後も利用者が安心して地域で生活を継続できるよう、医療機関や行政とも連携し、切れ目のないサポート体制を構築します。
老健の利用にかかる費用の内訳と目安

老健を利用する際にかかる費用は、主に介護保険が適用される「施設サービス費」と、全額自己負担となる「居住費」「食費」「日常生活費」の4つで構成されます。施設サービス費は、要介護度や施設の体制、所得に応じて1割から3割の自己負担となります。
一般的には所得に応じて1割負担の方が大半です。
月々の費用は、部屋のタイプ(多床室か個室か)や受けるサービス内容によって変動するため、事前に確認することが重要です。
【要介護度別】月額費用のシミュレーション
月額費用の目安は、要介護度や部屋のタイプによって大きく異なります。例えば、多床室を利用し、自己負担が1割の場合、施設サービス費、居住費、食費を合計した月額費用は、要介護1で約9万円、要介護3で約10万円、要介護5で約11万円程度が一般的です。
個室を利用する場合は、これに加えて3万円から5万円程度上乗せされることが多いです。この金額はあくまで目安であり、施設が提供するリハビリテーションの内容や加算サービスの有無によって変動します。
正確な費用については、入居を検討している施設に直接問い合わせて確認してください。
入居一時金などの初期費用はかからない
老健は、民間の有料老人ホームなどで必要となることが多い、高額な入居一時金や権利金といった初期費用が一切かかりません。これは、老健が介護保険法に基づく公的な施設であり、利用は施設との直接契約というよりは介護保険制度上の措置に近い位置づけであるためです。
そのため、まとまった初期費用を用意することなく、月々の利用料のみで入所できるのが大きな特徴です。これにより、経済的な負担を抑えつつ、必要な期間、集中的なリハビリと医療ケアを受けることが可能になります。
ただし、ごく稀に保証金を求められる施設もあるため、契約前に確認しておきましょう。
老健を利用する4つのメリット

老健の利用には、在宅復帰という明確な目的を支えるための多くのメリットがあります。最大の強みは、医師の管理のもとで専門的なリハビリを集中して受けられる点です。
また、看護師が常駐しているため医療ケアの体制も整っており、安心して療養生活を送れます。さらに、他の介護施設と比較して費用負担を抑えやすいことや、特別養護老人ホームよりも低い要介護度から入所を検討できる点も、利用者や家族にとって大きなメリットと言えるでしょう。
専門スタッフによる集中的なリハビリが受けられる
老健の最大のメリットは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリの専門家が常駐し、個々の状態に合わせた集中的な訓練を受けられる点です。医師が作成するリハビリテーション計画に基づき、身体機能の回復や日常生活動作の向上を目指したプログラムが提供されます。
他の介護施設、例えば特別養護老人ホームでは機能維持を目的とした訓練が主ですが、老健では「機能回復」を明確な目標に掲げているため、より積極的で専門性の高いリハビリが期待できます。病院退院後の体力低下からの回復を目指す方にとって最適な環境です。
医療ケアの体制が整っているため安心できる
医師が常勤し、看護師が24時間体制で配置されているため、医療的なケアが必要な方でも安心して入所できます。日々の健康管理はもちろん、喀痰吸引や経管栄養、インスリン注射などの医療処置にも対応可能な施設が多くあります。
急な体調変化にも迅速に対応できるため、医療依存度の高い方や、退院直後で体調が不安定な方にとって心強い環境です。一般的な有料老人ホームなどと比較して医療体制が充実している点は、老健の大きな強みの一つであり、本人だけでなく家族の安心にもつながります。
特別養護老人ホームなどの施設より費用を抑えやすい
老健は公的な介護保険施設であるため、民間の有料老人ホームに比べて利用料金が比較的安価に設定されています。また、入居時に高額な一時金が不要である点も、経済的な負担を大きく軽減します。
同じ公的施設である特別養護老人ホーム(特養)と比較した場合、老健は短期利用が前提であることや、多床室が中心であることなどから、月々の費用を抑えやすい傾向にあります。費用を抑えながら、一定期間、集中的なリハビリと医療ケアを受けたい場合に適した選択肢と言えます。
要介護1という比較的軽い段階から入所を検討できる
老健の入所条件は要介護1以上であり、特別養護老人ホーム(特養)が原則要介護3以上である点と大きな違いがあります。これにより、比較的介護度が低い段階からでも、専門的なリハビリを受ける目的で入所を検討できます。
例えば、骨折後の手術を経て、在宅生活に戻るにはまだリハビリが必要といったケースで活用しやすいのが特徴です。身体機能の回復が見込める早期の段階で集中的なケアを開始できることは、その後の在宅生活の質を大きく左右する重要なポイントになります。
知っておきたい老健の3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、老健にはその特性ゆえのデメリットも存在します。最も大きな点は、在宅復帰を目的としているため、終身利用ができず長期的な入所は認められないことです。
また、居室はプライバシーの確保が難しい多床室が中心であることや、生活の楽しみとなるレクリエーションが少ない傾向にあることも、事前に理解しておくべき点です。これらのデメリットを知ることで、入所後のミスマッチを防ぎ、本人にとって最適な選択ができるようになります。
終身利用はできず長期的な入所は認められない
老健はあくまで在宅復帰を目指すための一時的なリハビリ施設であり、「終の棲家」にはなり得ません。
入所期間は原則として3ヶ月から6ヶ月と定められており、この期間内に在宅復帰の目処を立てる必要があります。そのため、看取りまで含めた長期的な介護を希望する場合や、家族の介護負担の恒久的な軽減を目的とする場合には適していません。
退所が近づくと、在宅での介護サービスの調整や、場合によっては次の入所施設を探す必要が出てくるため、入所中から退所後の生活を見据えた準備が求められます。
プライバシー確保が難しい多床室が中心
多くの老健では、居室のタイプが4人部屋などの多床室となっています。
多床室は、他の入所者と生活空間を共有するため、プライバシーの確保が難しいという側面があります。カーテンで仕切られてはいるものの、同室者の生活音やいびきが気になったり、人間関係でストレスを感じたりする可能性は否定できません。
近年はプライバシーに配慮した個室やユニット型の施設も増えていますが、その分、居住費が高額になる傾向にあります。静かな環境で過ごしたい方や、一人の時間を大切にしたい方は、個室の有無を確認することが重要です。
生活を豊かにするレクリエーションやイベントは少なめ
老健の第一の目的はリハビリによる在宅復帰であるため、生活に彩りを加えるレクリエーションやイベントは、他の介護施設に比べて少ない傾向があります。
日中のスケジュールはリハビリが中心に組まれており、集団での体操や季節行事などは行われるものの、その頻度や内容は限定的であることが多いです。
有料老人ホームのように、多彩なアクティビティやサークル活動を期待すると、物足りなさを感じるかもしれません。施設での生活に楽しみや他者との交流を重視する場合は、見学の際にレクリエーションの実施状況を確認することをおすすめします。
老健への入居申し込みから契約までの6ステップ

老健への入所を具体的に進めるには、いくつかの段階的な手続きが必要です。
まず、公的な介護サービスを利用するための要介護認定の申請から始まります。認定を受けた後、希望に合う施設を探し、申し込み、面談、書類提出という手順を踏みます。
その後、施設側での入所判定を経て、契約を結び、晴れて入所となります。各ステップを順序立てて理解し、計画的に進めることで、スムーズな入所を実現できます。
ステップ1:要介護認定を申請して受ける
老健に入所するためには、まず前提として市区町村から要介護認定を受ける必要があります。
まだ認定を受けていない場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターで申請手続きを行います。申請後、認定調査員が自宅などを訪問して心身の状態を調査し、主治医が作成する意見書とあわせて審査が行われます。
その結果、要支援1・2、または要介護1~5のいずれかの区分が通知されます。老健への入所には要介護1以上の認定が必要であり、申請から結果が出るまで約1ヶ月かかるため、早めの行動が肝心です。
ステップ2:施設を探して入居を申し込む
要介護認定を受けたら、次に入所を希望する老健を探します。
担当のケアマネジャーや入院中の病院のソーシャルワーカー、地域包括支援センターに相談すると、本人の状態や希望に合った施設を紹介してもらえます。施設のウェブサイトや自治体が提供する情報も参考に、複数の候補をリストアップしましょう。
可能であれば必ず施設見学を行い、リハビリの様子やスタッフ、施設の雰囲気などを直接確認することが大切です。入所したい施設が決まったら、所定の申込書に必要事項を記入し、提出します。
ステップ3:担当者と本人・家族で面談を行う
申し込みをすると、施設の支援相談員や看護師といった担当者との面談が設定されます。この面談の役割は、本人の心身の状態、病歴、普段の生活の様子、リハビリへの意欲などを施設側が正確に把握することです。
これにより、施設で適切なケアやリハビリを提供できるかを判断します。家族は、本人の性格や好み、介護する上での悩み、施設に期待することなどを具体的に伝えることが重要です。
面談は本人が入院中であれば病院で、在宅であれば自宅で行われることが一般的です。
ステップ4:必要な書類を準備して提出する
面談と並行して、入所判定に必要な書類を準備し、施設へ提出します。一般的に求められるのは、入所申込書、介護保険被保険者証のコピー、健康保険証や後期高齢者医療被保険者証のコピー、そして主治医が作成した診療情報提供書(紹介状)です。
診療情報提供書には、病状や治療内容、服薬情報などが詳細に記載されており、施設側が医学的な受け入れ可否を判断するための重要な資料となります。この仕組みを通じて、入所後に安全で適切なサービスを提供するための情報共有が行われます。
ステップ5:施設側での入居判定の結果を待つ
提出された書類と面談で得られた情報をもとに、施設内で入居判定会議が開かれます。
この会議には、医師、看護師、リハビリ専門職、介護職員、支援相談員など、様々な専門職が参加します。本人の状態が施設の受け入れ基準を満たしているか、リハビリによって在宅復帰が見込めるか、どの居室区分が適切かなどを総合的に検討し、入所の可否を決定します。
判定結果は、通常1週間から2週間ほどで電話や郵送にて本人や家族に伝えられます。入所可能となれば、具体的な入所日の調整に入ります。
ステップ6:契約手続きを済ませて入居する
入所日と利用する部屋が決定したら、施設との間で正式な利用契約を締結します。契約時には、施設の担当者から重要事項説明書に基づき、サービス内容、利用料金、規則などについて詳しい説明があります。内容を十分に理解し、疑問点がないか確認した上で署名・捺印をします。
契約と並行して、衣類や洗面用具、室内履きなど、入所に必要な身の回り品の準備を進めます。すべての手続きと準備が整ったら、決定した入所日に施設での生活がスタートし、在宅復帰に向けた介護やリハビリが開始されます。
まとめ

介護老人保健施設(老健)は、病院から退院した後、すぐに在宅での生活に戻ることが難しい方が、リハビリテーションを通じて在宅復帰を目指すための中間施設です。医師や看護師による医療的管理と、理学療法士などによる専門的なリハビリを同時に受けられる点が大きな特徴です。
入所期間は原則として3ヶ月から6ヶ月と短期間であり、要介護1という比較的軽い段階から利用できます。看取りまでを視野に入れた長期的な生活の場である特別養護老人ホームとは、その目的や役割が明確に異なります。
こうした特性を理解し、本人の状態や目的に合わせて施設を選択することが重要です。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。