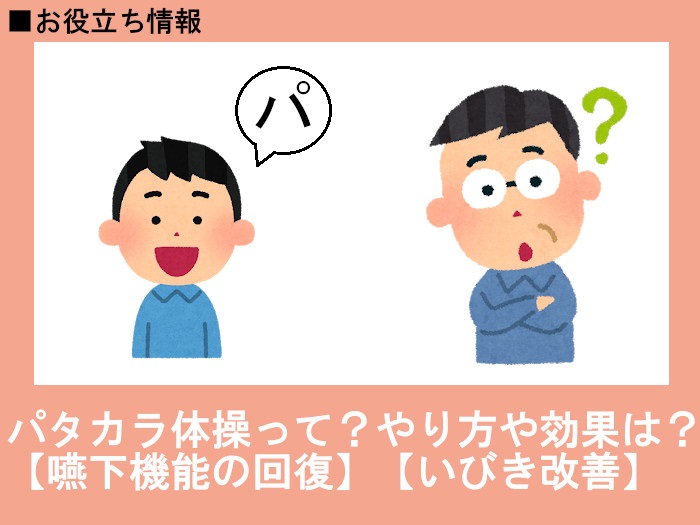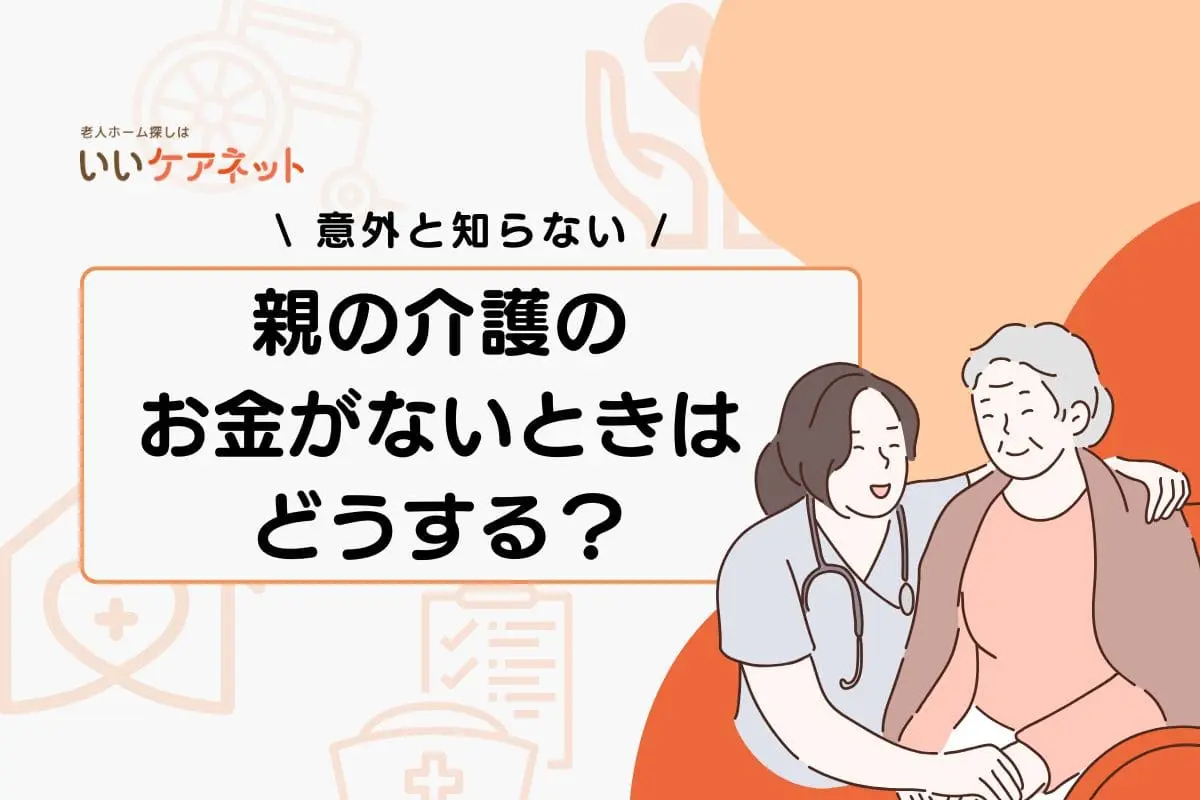ショートステイの利用を考え始めたとき、多くの方が気になるのが費用の相場です。ショートステイの費用は、利用する施設の種類や要介護度、部屋のタイプによって変動します。
この記事では、ショートステイの基本的なサービス内容から、費用の内訳、介護保険の適用条件、そして費用負担を軽減するための公的制度までを網羅的に解説します。具体的な料金シミュレーションも交えながら、ご自身の状況に合わせた費用の目安を把握できるように説明していきます。
そもそもショートステイとは?短期間だけ施設に宿泊できる介護サービス

ショートステイとは、高齢者が数日から数週間といった短期間だけ介護施設に入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられる介護サービスです。正式名称は「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」と言います。
主な目的は、在宅介護を行う家族の身体的・精神的な負担を軽減する「レスパイトケア」ですが、利用者本人の心身機能の維持や、在宅での孤立感の解消といった役割も担っています。将来的な施設入所を見据えたお試し利用として活用されることもあります。
ショートステイ滞在中に受けられる具体的なサービス内容
ショートステイ滞在中には、日常生活を支えるための様々なサービスが提供されます。中心となるのは、食事の提供、入浴の介助、トイレへの誘導や排泄の介助といった身体介護です。
これらに加えて、レクリエーションや体操などの機能訓練を通じて、利用者の心身機能の維持・向上を図ります。
多くの施設では、自宅と施設の間を送迎してくれるサービスも提供しており、家族の送迎負担を軽減できます。また、看護職員による健康管理や服薬のサポートも受けられるため、医療的なケアが必要な方も安心して過ごすことが可能です。他の利用者との交流の機会は、社会的な孤立を防ぐ上でも重要な役割を果たします。
ショートステイで利用できる居室の種類とそれぞれの特徴
ショートステイで利用できる居室にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や宿泊費が異なります。最も一般的なのは、複数のベッドが一部屋に設置された「多床室」で、料金が安価な点がメリットですが、プライバシーの確保は難しくなります。
一方、「個室」はプライバシーが保たれるため、落ち着いた環境で過ごしたい方に適しています。個室には、洗面台やトイレが共用の「従来型個室」と、10人程度の少人数グループを一つの生活単位とし、リビングなどの共用スペースを囲むように個室が配置された「ユニット型個室」があります。
ユニット型はより家庭的な雰囲気で過ごせる分、費用は高くなる傾向にあります。
ショートステイで発生する費用の詳しい内訳を解説

ショートステイの利用料金は、複数の費用項目を合算して計算されます。主な内訳は、介護保険が適用される「介護サービス費」と、保険適用外で全額自己負担となる「滞在費」「食費」、そして理美容代や個人の希望で購入する嗜好品などの「その他の費用」の4つです。
これらの費用は、施設の種別や要介護度、居室のタイプによって金額が変わるため、最終的な利用料金を把握するには、それぞれの内訳を理解しておくことが重要です。
介護保険が適用される「介護サービス費」
介護サービス費は、ショートステイで提供される介護サービスそのものにかかる費用であり、介護保険が適用される部分です。利用者は、所得に応じてこの費用の1割から3割を自己負担します。
具体的な金額は、厚生労働省が定める「介護報酬単位」に基づいて算出され、利用者の要介護度が高いほど、また施設の体制が手厚いほど高くなります。
例えば、職員の配置が手厚い施設には「サービス提供体制強化加算」が、送迎を利用した場合には「送迎加算」が上乗せされる仕組みです。これらの加算も介護保険の対象となり、自己負担額に反映されます。
介護保険適用外となる「滞在費」と「食費」
ショートステイの利用にかかる費用のうち、滞在費と食費は介護保険の適用対象外となり、原則として全額自己負担です。滞在費は、いわゆる部屋代のことで、多床室か個室かといった居室のタイプによって金額が大きく異なります。食費は、施設から提供される食事にかかる費用で、1日3食分が請求されるのが一般的です。
これらの費用は施設が独自に設定できるため、施設ごとに料金体系が異なります。有料老人ホームなどが提供するショートステイでは、これらの費用が比較的高額になる傾向が見られます。ただし、所得の低い方を対象に、これらの負担を軽減する制度も用意されています。
理美容代や娯楽費など「日常生活でかかるその他の費用」
介護サービス費や滞在費・食費の他に、利用者の日常生活において必要となる様々な費用が別途発生します。これらは「その他の費用」として区分され、全額が自己負担となります。具体的には、施設内で受ける理美容サービス代、特別な材料が必要なレクリエーションの参加費、個人で楽しむテレビカードの購入費などが挙げられます。
また、おむつ代や歯ブラシといった日用品費も、施設によっては自己負担となる場合があります。何が基本料金に含まれ、何が別途費用となるのかは施設によって異なるため、契約前にサービス内容と料金体系を細かく確認しておくことが重要です。
【種類別】ショートステイの費用相場を料金シミュレーションで紹介

ショートステイの費用がどのくらいかかるのか、具体的な目安を知りたい方も多いでしょう。1日あたりの費用は、施設の種類、利用者の要介護度、居室のタイプ、そして介護保険の自己負担割合によって変動します。
ここでは、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類について、要介護度や部屋のタイプごとに1日あたりの料金目安を示します。ご自身の状況に近いケースを参考に、おおよその自己負担額をシミュレーションしてみてください。
「短期入所生活介護」の1日あたりの料金目安
短期入所生活介護は、特別養護老人ホームなどに併設されている一般的なショートステイです。費用は要介護度や居室タイプによって異なります。例えば、自己負担1割の方が利用する場合、1日あたりの費用の目安は以下のようになります。
多床室を利用した場合、要介護1で約2,500円、要介護3で約2,800円、要介護5で約3,100円程度です。
これが従来型個室になると、要介護1で約3,300円、要介護3で約3,600円、要介護5で約3,900円となります。これらの金額は介護サービス費、滞在費、食費を合計した概算であり、施設や加算の有無によって変動します。
医療ケアにも対応する「短期入所療養介護」の料金目安
短期入所療養介護は、介護老人保健施設(老健)や療養病床を持つ病院などで提供される、医療的ケアが充実したショートステイです。医師や看護師が常駐し、リハビリ専門職も配置されているため、短期入所生活介護よりも費用は高くなる傾向にあります。自己負担1割の方が介護老人保健施設の従来型個室を利用した場合、1日あたりの費用目安は、要介護1で約3,800円、要介護3で約4,500円、要介護5で約5,100円程度です。
医療的ケアや専門的なリハビリが必要な高齢者にとって、安心して療養できる環境が提供されます。
部屋のタイプ(多床室・個室)によって費用はどう変わる?
ショートステイの費用を大きく左右する要素の一つが、部屋のタイプです。複数の利用者が同じ部屋で過ごす「多床室」は、滞在費が最も安く設定されており、経済的な負担を抑えたい場合に適しています。一方、プライバシーを確保できる「個室」は、滞在費が高くなります。
例えば、介護施設「そよ風」の料金例を見ると、滞在費は多床室と個室で1日あたり1,000円以上の差がつくこともあります。ユニット型個室は、さらに高額になる傾向があります。費用面だけでなく、本人の性格や希望する過ごし方を考慮して、多床室での交流を好むか、個室で静かに過ごしたいかなどを検討して部屋のタイプを選ぶことが大切です。
ショートステイで介護保険を利用するための条件

ショートステイの費用負担を軽減するためには、介護保険の適用が不可欠です。しかし、ショートステイを利用するには、誰でも介護保険を使えるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
具体的には、要介護認定を受けていることや、連続して利用できる日数に上限があることなどが定められています。これらのルールを正しく理解し、計画的に利用することが、サービスの有効活用につながります。
要支援・要介護認定を受けていることが必須
介護保険を適用してショートステイを利用するための最も基本的な条件は、お住まいの市区町村から「要支援」または「要介護」の認定を受けていることです。要支援1・2の認定を受けた方は「介護予防短期入所生活介護」や「介護予防短期入所療養介護」の対象となり、介護予防を目的としたサービスを利用できます。
一方、要介護1〜5の認定を受けた方は「短期入所生活介護」や「短期入所療養介護」の対象です。まだ認定を受けていない場合は、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請手続きを行う必要があります。
介護保険が使える連続利用日数は30日まで
介護保険を使ってショートステイを利用する場合、連続して利用できる日数は原則として最大30日までと定められています。もし30日を超えて利用を継続した場合、31日目からは介護保険が適用されず、サービス費を含めて全額が自己負担となるため注意が必要です。
また、連続利用日数が30日以内であっても、介護保険の利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにケアプランを作成するというルールも存在します。特別な事情がある場合や、長期利用を前提とした「ロングショートステイ」を受け入れている施設もありますが、費用や条件については事前にケアマネジャーへの確認が不可欠です。
ショートステイの費用負担を軽減するための4つの公的制度

ショートステイの利用が長期間に及んだり、他の介護サービスと併用したりすると、月々の費用負担は決して少なくありません。しかし、利用者の経済的な状況に応じて、その負担を軽くするための公的な制度がいくつか用意されています。
これらの制度をうまく活用することで、自己負担額を大幅に抑えることが可能です。ここでは、ショートステイの費用負担を軽減するために知っておきたい4つの代表的な制度について、それぞれの内容と適用条件を解説します。
滞在費・食費が安くなる「負担限度額認定制度」
負担限度額認定制度は、所得や預貯金が一定基準以下の利用者を対象に、介護保険適用外である滞在費と食費の自己負担額に上限(基準額)を設ける制度です。この制度を利用すると、設定された負担限度額を超えた分の金額が、介護保険から「特定入所者介護サービス費」として施設に支払われるため、自己負担を軽減できます。
対象となるのは、本人および世帯全員が住民税非課税であること、配偶者がいる場合は配偶者も住民税非課税であること、預貯金等の資産が一定額以下であることなどの条件を満たす方です。制度を利用するには、市区町村の窓口へ申請し、「負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
自己負担額の上限を超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」
高額介護サービス費制度は、同じ月に利用した介護サービスの自己負担額の合計が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。この制度は、ショートステイだけでなく、デイサービスや訪問介護など他の介護保険サービスの利用者負担額も合算して計算されます。同じ世帯内に複数の介護サービス利用者がいる場合は、その負担額を世帯で合算することが可能です。
ただし、福祉用具購入費や住宅改修費、そしてショートステイにおける食費や滞在費、その他の日常生活費は対象外となるため注意が必要です。この制度は医療費控除とは異なります。
自治体が独自に行っている助成金や補助金制度
国の公的制度に加えて、市区町村が独自にショートステイ利用者のための助成金や補助金制度を設けている場合があります。制度の内容は自治体によって大きく異なり、例えば、介護者の急病や冠婚葬祭といった緊急時の利用料を補助するものや、低所得者世帯を対象に利用料の一部を助成するものなど多岐にわたります。
東京都世田谷区のように、独自の基準で利用料の助成を行っている自治体もあります。お住まいの地域でどのような制度が利用できるかについては、市区町村の高齢者福祉担当窓口や、担当のケアマネジャー、地域包括支援センターなどに問い合わせて確認することをおすすめします。
医療費控除の対象となるケースについて
ショートステイの利用料の一部は、確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。対象となるのは、主に「短期入所療養介護(医療型ショートステイ)」を利用した場合です。介護老人保健施設や介護医療院などで提供されるこのサービスでは、自己負担した介護費、食費、居住費が医療費控除の対象に含まれます。
一方、「短期入所生活介護(福祉型ショートステイ)」の利用料は原則として対象外ですが、看護師による喀痰吸引などの特定の医療ケアを受けた場合は、その分の費用が対象になることがあります。控除を受けるためには領収書が必要となるため、必ず保管しておきましょう。
相談から利用開始まで|ショートステイ手続きの4ステップ

実際にショートステイの利用を考えたとき、何から手をつければ良いのか戸惑うこともあるかもしれません。
スムーズに利用を開始するためには、手続きの全体的な流れを事前に把握しておくことが大切です。ここでは、担当のケアマネジャーへの相談から始まり、施設の見学、面談を経て、契約し利用を開始するまでを、分かりやすく4つのステップに分けて解説します。
この手順に沿って進めることで、安心して手続きを進めることができます。
ステップ1:担当ケアマネジャーへ利用希望を伝える
ショートステイを利用するには、まず担当のケアマネジャーに相談することから始めます。
要介護認定を受けている方は担当ケアマネジャー、要支援認定の方は地域包括支援センターの担当者が窓口です。
相談の際は、なぜ利用したいのか(例:介護者の休息、旅行、冠婚葬祭)、いつからいつまで利用したいのか、本人の健康状態や希望する過ごし方などをできるだけ具体的に伝えましょう。ケアマネジャーはこれらの情報を基に、利用者の状況に合った施設を探し、ケアプランにショートステイの利用を位置づけるための調整を行ってくれます。
ステップ2:条件に合う施設を探して見学を申し込む
ケアマネジャーからいくつかの候補施設が提案されたら、それぞれの特徴を比較検討します。料金やサービス内容はもちろんですが、施設の雰囲気や職員の対応などを知るために、可能な限り施設見学を行いましょう。
見学の際には、居室や共用スペースの清潔さ、食事の内容、レクリエーションの様子、他の利用者の表情などを直接確認することが重要です。利用者本人も同行できると、滞在中の生活をイメージしやすくなります。疑問に思ったことや不安な点は、その場にいる職員に遠慮なく質問し、納得のいく施設選びを心がけましょう。
ステップ3:利用したい施設で担当者と面談を行う
利用したい施設が決まったら、次に施設の担当者との面談が行われます。この面談には、利用者本人と家族、そしてケアマネジャーが同席するのが一般的です。
面談では、施設側から利用者の心身の状態、既往歴、服薬状況、食事の形態、アレルギーの有無、日常生活での留意点などについて詳細なヒアリングがあります。これは、施設が利用者に安全で適切なサービスを提供できるかを判断するための重要なプロセスです。同時に、利用者側からも施設での過ごし方に関する希望や、配慮してほしい点を具体的に伝える良い機会となります。
ステップ4:契約内容を確認して利用開始日を決める
面談の結果、施設側で受け入れ可能と判断されると、正式な契約手続きへと進みます。契約書や重要事項説明書には、提供されるサービスの詳細な内容、利用料金とその内訳、キャンセル料の規定、緊急時の対応方法などが明記されています。特に、基本料金以外にどのような場合に別途費用が発生するのかは、トラブルを避けるためにも必ず確認しましょう。
すべての内容をよく読み、不明点がないことを確認した上で署名・捺印します。契約が完了したら、ケアマネジャーや施設と相談して具体的な利用開始日を決定し、いよいよ利用がスタートします。
まとめ

ショートステイの費用は、介護保険の自己負担分である「介護サービス費」と、全額自己負担となる「滞在費」「食費」「その他の実費」の合計で決まります。その金額は、利用する施設が福祉中心か医療ケアも提供するか、要介護度はどのくらいか、居室は多床室か個室かといった条件で大きく変動します。
費用負担を軽減するためには、所得に応じて滞在費・食費の上限額が設定される「負担限度額認定制度」や、自己負担額の合計が上限を超えた際に払い戻される「高額介護サービス費」などの公的制度の活用が有効です。
最適な施設を選び、費用を抑えながらサービスを利用するためには、まず担当のケアマネジャーに相談し、自身の状況に合った利用計画を立てることが重要です。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。