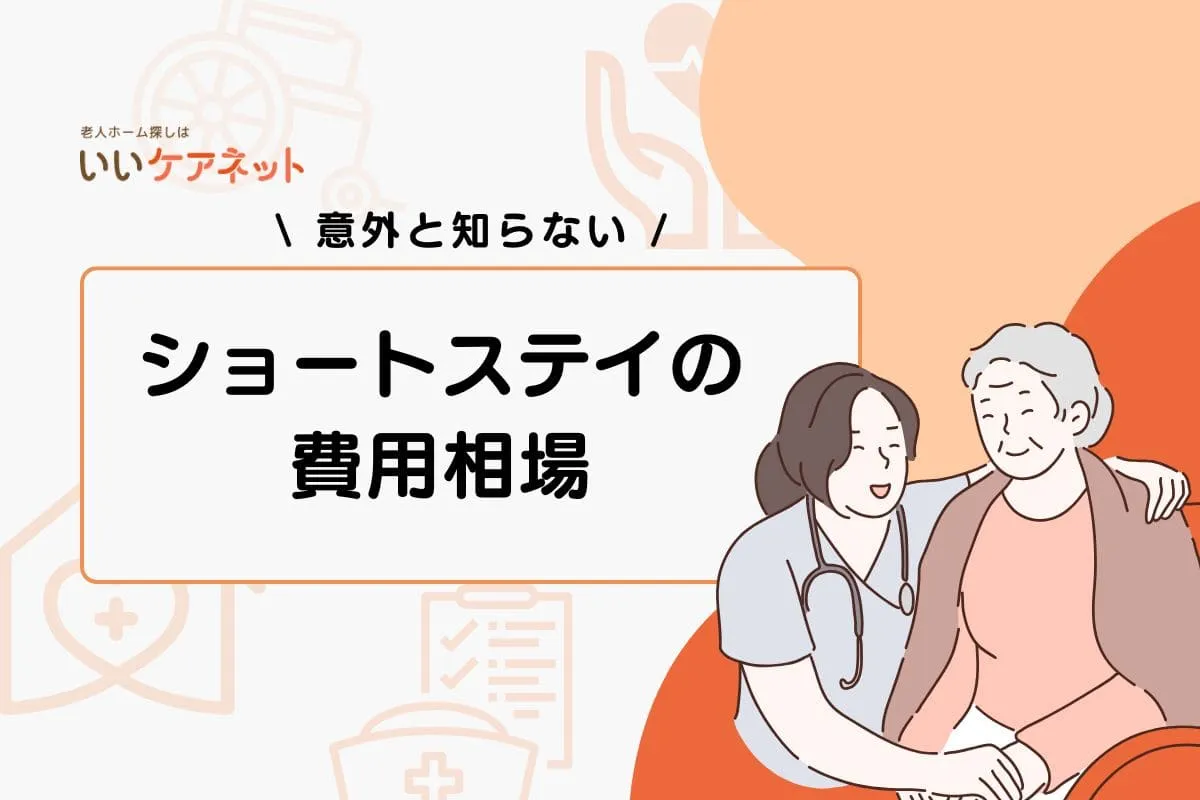前回の訪問看護における別表7の疾病について【PART1】に引き続き、以下の疾病の解説を行います。
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳症
ご家族や支援者の理解を深める助けになるよう、ポイントをわかりやすく解説します。
ハンチントン病について

ハンチントン病は、主に運動機能と認知面に影響を及ぼす神経変性疾患です。
遺伝子変異の繰り返し数が多いほど若年期発症の傾向が強まる疾病です。
ハンチントン病の原因
ハンチントン病は、体の中の「HTT(エイチティーティー)」という遺伝子に異常が起きることで発症します。この遺伝子の中に「CAG」という文字列があり、これが通常よりも多く繰り返されていると、体に悪影響をもたらします。
この異常によって作られた「ハンチンチン」というたんぱく質が脳にたまり、運動や考える力をつかさどる「線条体(せんじょうたい)」や「大脳皮質(だいのうひしつ)」の働きが乱れ、体の動きや思考、感情のコントロールに支障が出てるのが特徴です。
ハンチントン病は遺伝する病気で、性別に関係なく遺伝子異常が50%の確率で子孫に伝わります。発症年齢は30〜50歳が多いとされており、高齢で発症することもあります。
ハンチントン病の主な症状
ハンチントン病には、以下のような症状があります。
- 舞踏運動を中心とする不随意運動
- 運動の持続障害
- 精神症状
不随意運動は上肢や下肢に限らず顔面や体幹にも及ぶため、本人の意思とは無関係に動作が生じやすくなります。
また、認知機能の低下や精神症状も見過ごせません。集中力や判断力が落ち、抑うつや幻覚、被害妄想などが表れるケースも報告されています。
発症初期はわずかな運動障害や気分の浮き沈み程度でも、病状が進むと対人コミュニケーションが難しくなることが多く、家族のケア負担が増大しやすい傾向があります。
最終的には寝たきり状態や重篤な認知障害に至るケースがあり、複数領域の専門職が連携した支援が欠かせません。
進行性筋ジストロフィー症について
進行性筋ジストロフィー症は、骨格筋の変性と筋力低下が続く遺伝性疾患です。
デュシェンヌ型が代表例で、小児期から歩行困難や転倒に直面する方もいます。
進行性筋ジストロフィー症の原因
進行性筋ジストロフィー症は、筋肉をつくる「遺伝子」に異常が起きる疾病です。
特に「デュシェンヌ型」になると、筋肉を守る「ジストロフィン」というたんぱく質がうまく作られません。このたんぱく質が不足すると、筋肉の細胞が壊れやすくなります。
日常の動作やちょっとした動きでも筋肉が傷つきやすくなり、その修復を繰り返すうちに、筋肉がかたくなったり、動きづらくなったりして徐々に筋力が低下します。
一方、症状が比較的ゆるやかに進むのが「ベッカー型」というタイプです。
進行性筋ジストロフィー症は、男性に多く見られます。「X染色体」と呼ばれる性別に関わる部分に異常が起きるため、女性より男性のほうが発症しやすい疾病です。
進行性筋ジストロフィー症の主な症状
進行性筋ジストロフィー症の主な症状は、筋力低下の進行です。
発症初期は歩き方が不安定になったり転倒しやすくなったりし、時間とともに起き上がり動作や階段昇降などが難しくなります。
特にデュシェンヌ型では学童期に急速な筋力低下が進み、車椅子が必要となるケースも珍しくありません。上肢の筋力も次第に衰え、食事や更衣などの日常動作に支障をきたすこともあります。
進行すると心筋や呼吸筋などの筋力も低下し、心不全や呼吸不全が重篤化するリスクがあります。
徐々に自力歩行が出来なくなり車椅子生活を余儀なくされたり、呼吸を司る筋肉が強く影響を受けて呼吸障害を起こしたり、嚥下機能に悪影響が生じ、誤嚥性肺炎を繰り返すこともある疾病です。
パーキンソン関連疾患について

パーキンソン関連疾患には、パーキンソン病や進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症などが含まれます。
それぞれの原因や症状は異なるため、順に解説します。
パーキンソン病
パーキンソン病は、ドーパミンをつくる神経細胞が壊れていくことで発症します。
詳しい原因と主な症状は、以下のとおりです。
パーキンソン病の原因
パーキンソン病の原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝と環境の両方が関係していると考えられています。
いくつかの遺伝子の変化が発症しやすさに影響するとされており、農薬や金属などの環境的な影響も懸念されています。
パーキンソン病は、一つの原因だけでは説明できない複雑な疾病です。年齢を重ねるにつれて自然に神経細胞が減っていくことが、パーキンソン病の発症に拍車をかけることもあります。
進行を完全に止める方法はまだ見つかっていません。今も国内外で、パーキンソン病の解明や新しい治療法の研究が続けられています。
パーキンソン病の主な症状
パーキンソン病の主な症状は、以下のとおりです。
- 体の震え
- 嗅覚障害
- 便秘
パーキンソン病で特徴的なのは、「安静時振戦(しんせん)」と呼ばれる震えです。手や足が何もしていないときに小さく震えることがあり、緊張やストレスによって強くなることもあります。
また、「筋強剛(きんきょうごう)」という筋肉のこわばりが進むと、動き始めに時間がかかったり動作の切り替えがうまくいかなくなる「無動(むどう)」の症状が目立つようになったりします。
体の動き以外にも、さまざまな不調が現れるのがパーキンソン病の特徴です。
便秘、においがわかりにくくなる嗅覚障害、寝つきの悪さや眠りの浅さなどの不調が見られます。気分が落ち込んだり、やる気が出なくなったりすることもあります。
パーキンソン病は症状が多く、他の病気と見分けが難しいこともあり、診断が確定するまでに時間がかかる疾病です。
進行性核上性麻痺
進行性核上性麻痺は、神経変異が原因で発症します。
詳しい原因と主な症状を解説します。
進行性核上性麻痺の原因
進行性核上性麻痺は、脳の神経細胞に「タウ蛋白(たんぱく)」という物質が異常に溜まってしまうことが原因です。
タウ蛋白が溜まってしまうと線維状に固まりやすくなり、神経細胞の働きを妨げてしまいます。
脳幹(のうかん)や大脳基底核(だいのうきていかく)、そして前頭葉の皮質などの重要な部分に影響が及びます。
遺伝の影響については、まだはっきりしていません。生活環境や体への負荷など、さまざまな外部要因が関係している可能性も指摘されています。
進行性核上性麻痺の主な症状
進行性核上性麻痺を発症すると、以下のような症状があらわれます。
- 視力障碍
- 筋力低下
特に、目を上下に動かす力が弱くなっていく「垂直方向の眼球運動障害」が目立ちます。
特に、上や下を向こうとしたときに視線がスムーズに動かせず、足元を確認しにくくなるため、つまずいたり転倒したりすることが多くなります。
また、筋肉がこわばる「筋強剛」や、動作がゆっくりになる「無動」など、パーキンソン病に似た症状が出るのも進行性核上性麻痺の特徴です。
さらに、食べ物を飲み込む力(嚥下機能)にも影響が出ることがあり、誤って食べ物が気管に入る「誤嚥(ごえん)性肺炎」への注意も必要です。
大脳皮質基底核変性症
大脳皮質基底核変性症は、神経細胞の機能不全を引き起こす疾病です。
原因と主な症状について、詳しく解説します。
大脳皮質基底核変性症の原因
大脳皮質基底核変性症は、脳の中に異常なたんぱく質が溜まり、神経細胞がうまく働かなくなる疾病です。
脳の「皮質(ひしつ)」と「基底核(きていかく)」という2つの部分が同時にダメージを受け、さまざまな運動障害や認知の問題があらわれます。
今のところ、遺伝の関与は確認されていません。なぜこの病気が起こるのか、その仕組みにはまだ多くの謎が残っています。
発症は高齢者に多いとされていますが、40〜50代で始まる例もあります。予防法は確立されておらず、早期に防ぐのは難しいのが現状です。
大脳皮質基底核変性症の主な症状
大脳皮質基底核変性症の主な症状は、以下のとおりです。
- 手や指が勝手に動く
- 認知機能の低下
- 筋肉のこわばり
- 感情表現の低下
なかでも注目されるのが「エイリアンハンド症候群」と呼ばれる症状で、本人の意思とは関係なく手や指が勝手に動くように感じることがあります。
勝手に衣服をつかんだり、ボタンを外したりするなど、意図しない行動を起こすのが特徴です。
また、歩きにくくなる、筋肉がこわばるなどの「パーキンソニズム」の症状も進行していきます。
さらに、「失行症」という状態もよく見られます。これは、道具の使い方がわからなくなったり、物の位置や並び方をうまく認識できなくなったりするものです。
大脳皮質基底核変性症は、身体の右と左のどちらか一方に症状が強く出るのが特徴です。
その他、表情が乏しくなったり言葉を話す力が弱くなったりすることで、まわりとのコミュニケーションが難しくなるケースも多く見られます。
多系統萎縮症について
自律神経障害の症状
多系統萎縮症では、自律神経の働きが大きく乱れ、血圧の調整・汗のかき方・排尿や排便のコントロールなどに深刻な影響が出ることがあります。
なかでも「起立性低血圧」はよく見られる症状で、ふらつきや失神を起こしやすくなるため歩行中にも注意が必要です。
排尿のトラブルも進行すると、トイレでうまく排せつできなくなり、管(カテーテル)を使って尿を出すこともあります。
夜間に何度もトイレに行きたくなる「夜間頻尿」や、排尿をうまくコントロールできない「失禁」は、本人だけでなく家族の負担にもつながります。
また、汗のかき方にも異常が現れ、汗をかかなくなったり必要以上に汗をかいたりするため、体温調整が困難になります。
パーキンソン症状(錐体外路症状)
多系統萎縮症のなかには、パーキンソン病に似た症状(パーキンソニズム)があります。
筋肉がかたくなる「筋強剛」、動きがゆっくりになる「動作緩慢」、手足がじっとしているときに震える「安静時振戦」などが主な症状です。
パーキンソン病と症状がよく似ているため、はじめは混同されることもあります。しかし、このタイプの多系統萎縮症は、薬が効きにくく、症状の進行が早いという違いがあります。
さらに、運動症状に加えて、自律神経の不調や、小脳がうまく働かなくなる「小脳失調」も同時に起こるのが多系統萎縮症の特徴です。
このため、単なるパーキンソン病とは異なり、より複雑な疾病といえます。
小脳性運動失調の症状
多系統萎縮症では、「小脳性運動失調(しょうのうせいうんどうしっちょう)」という症状もあります。
小脳性運動失調は、小脳の働きが低下することで、手足や体の動きを調整できなくなる状態です。
典型的なのが「失調歩行」と呼ばれるふらつきを伴う歩き方です。まっすぐ歩けなくなったり、バランスを崩しやすくなったりします。
また、手や足を思った位置に正確に動かすことが難しくなり、細かい作業がうまくできなくなることもあります。字を書く、ボタンを留めるといった日常の動作が不自由になっていくのが特徴です。
さらに、「構音障害(こうおんしょうがい)」といって、言葉をはっきり発音できなくなる症状が現れることもあります。
声が不明瞭になり、相手にうまく伝わらなくなることで、コミュニケーションに支障をきたす場合があります。
プリオン病について

プリオン病は、たんぱく質の異常で発症する疾病です。
進行が早いため、早期の発見が求められます。
プリオン病の原因
プリオン病は、体内にもともとある正常なたんぱく質が変異し、次々と異常な状態(異常プリオンたんぱく質)へ変わっていくことで発症します。
この異常プリオンたんぱく質が脳にたまると、神経細胞が傷つき、脳の組織がスポンジ状に変性します。
この病気の原因となる「プリオン」は、ウイルスや細菌と違って遺伝情報(核酸)を持たず、たんぱく質そのものが感染性を持っている点が特徴です。
プリオン病は男性よりもやや女性に多く、ひとたび発症すると進行が早い疾病です。
プリオン病の主な症状
プリオン病は、以下のような症状を引き起こします。
- 認知機能の低下
- 運動機能の低下
- 視力や聴力の低下
初期には「もの忘れが増えた」「集中できない」などの軽い認知の変化から始まるため、認知症として見過ごされやすい疾病です。
しかし、プリオン病は進行が速く、わずか数か月のうちに深刻な記憶障害や、物の使い方がわからなくなる「失行(しっこう)」、言葉が出なくなる「失語(しつご)」などが目立ってきます。
日常生活を一人で送るのが難しくなるケースも少なくありません。
また、歩いたりバランスを取ったりするのが難しくなる「運動失調」、筋肉が急にピクッと動く「ミオクローヌス」、筋肉のこわばりなどが重なり、身体の自由が大きく制限されていきます。
さらに、視力や聴力にも影響が出ることがあり、神経全体の働きがどんどん落ちていくのが特徴です
症状が進むと、意識がもうろうとするなどの「意識障害」にもつながり、発症から1年以内に命に関わるケースも多く見られます。
亜急性硬化症全脳炎について
亜急性硬化症全脳炎は、ウイルスが原因で発症する疾病です。
この疾病を発症しやすいのは学童期で全体の80%を占めています。
亜急性硬化症全脳炎の原因
亜急性硬化症全脳炎(SSPE)は、過去にかかった麻疹のウイルスが脳内に長期間とどまり、ゆっくり悪さを始めることで起こると考えられています。
麻疹に感染してから5〜10年の潜伏期間の後に発症するため、発見が遅れやすい疾病です。
はっきりとした原因は特定されていませんが、体質や免疫の働き方などが関係しているとされています。
ワクチンの普及で患者は減ってきましたが、根絶には至っていません。
亜急性硬化症全脳炎の主な症状
亜急性硬化症全脳炎の主な症状は、以下のとおりです。
- 認知機能の低下
- 神経症状
最初に「もの忘れが増える」「性格が変わったように感じる」などの精神・認知面の変化があらわれます。
続いて、けいれん発作や「ミオクローヌス」と呼ばれる体のぴくつきが見られるようになり、次第に神経症状が進行していくのが特徴です。
ミオクローヌスは、一定のリズムで全身がけいれんすることもあり、日常生活の動作に大きな支障をきたします。
視野が狭くなる、言葉がうまく話せなくなるといった症状が加わるケースもあり、本人と家族の負担が急速に大きくなります。
別表7に該当する方は訪問看護を検討しましょう

以上が訪問看護における別表7の各疾患の原因と主な症状です。どの疾病も日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
ご自宅での生活や介護が難しい方は、お気軽に「いいケアネット」へご相談ください。入居者様の症状を聞きとり、安心して過ごせる介護施設を探すお手伝いをいたします。
大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!
監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行
一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。